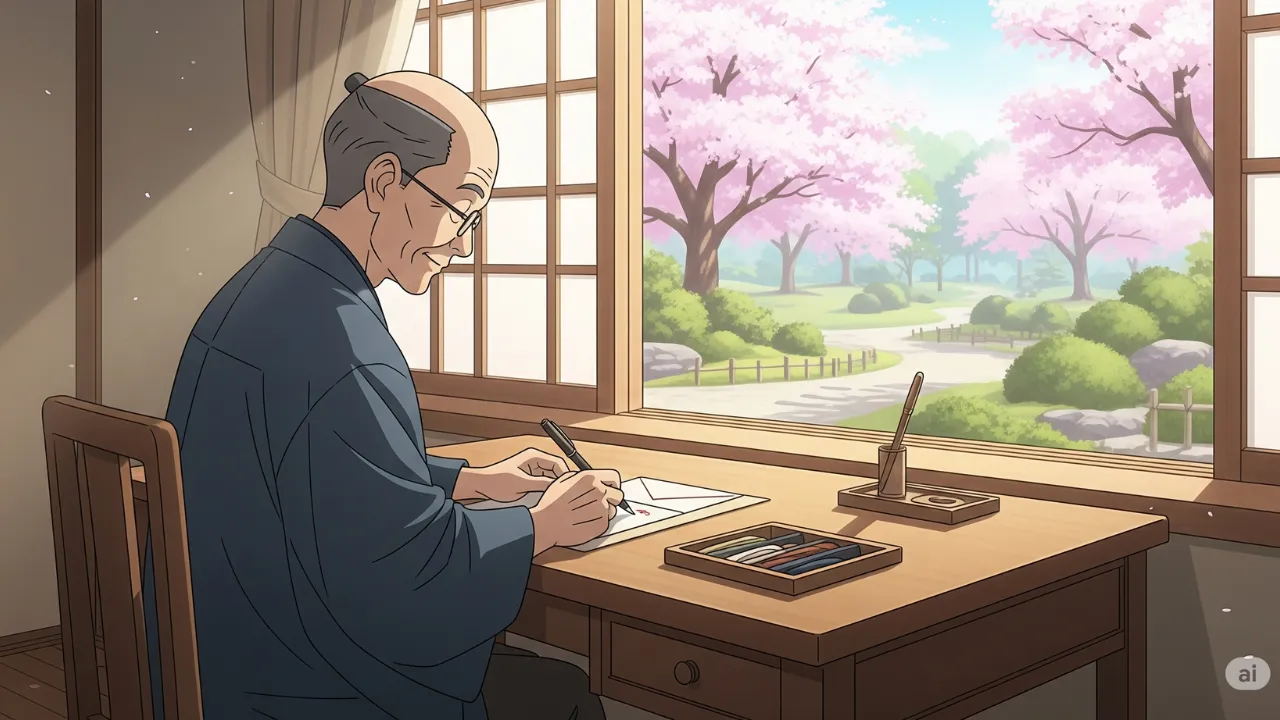遺言書の作成は、ご家族や大切な人へご自身の想いを形として残すための重要な手続きです。しかし、「どの遺言書キットを選べばよいかわからない」と迷う方も多いのではないでしょうか。この記事では、数ある製品の中から特におすすめの遺言書キットをご紹介します。
初心者でも簡単に使えるものから、法的な要件を満たした本格的なものまで、各キットの特徴を徹底解説します。さらに、遺言書キットを選ぶ際のポイントや具体的な使い方についても詳しくお届けしますので、作成時の不安を解消できるでしょう。
この記事を読めば、あなたに最適な遺言書キットが見つかります。将来の相続トラブルを防ぎ、ご家族の安心を守るための第一歩を、ここから始めてみませんか。
遺言書キットとは?その役割と基本的な特徴
遺言書キットとは、ご自身の意思を法的に有効な形で残すために、必要な道具や説明書が一つになった便利な商品です。「遺言書」と聞くと、専門知識が必要で難しいイメージを持つかもしれませんが、キットを使えば誰でも手軽に作成できます。
キットには通常、遺言書用の用紙や書き方の見本、詳しい解説書などが含まれています。これにより、財産の分け方やご自身の希望を明確に記録でき、将来の相続トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。終活の第一歩としても最適です。
遺言書キットの基本構成と内容
遺言書キットには、作成に必要な道具が一通り揃っています。具体的には、法的な要件を満たした専用の用紙、作成手順を記した解説書、保管用の封筒などが基本構成です。商品によっては、下書き用紙や文例集が付属しているものもあります。
特に解説書は、法律に詳しくない方でも理解しやすいように、図解やイラストを用いて説明されていることが多いです。初めての方でも迷わず書けるよう工夫されているため、安心して遺言書の作成に取り組むことができるでしょう。
遺言書キットを利用するメリットと注意点
遺言書キットを利用する最大のメリットは、手軽かつ低コストで遺言書を作成できる点です。弁護士などの専門家に依頼すると費用がかかりますが、キットなら手頃な価格で始められます。また、ご自身の言葉で想いを綴れる自由度の高さも魅力です。
一方で、法的な要件を満たさないと遺言書が無効になるリスクには注意が必要です。キットの説明書を熟読し、日付や署名、押印などの形式的な不備がないか確認しましょう。複雑な財産状況の場合は、専門家への相談も検討することをおすすめします。
遺言書作成で押さえるべき法律のポイント
遺言書を作成する際は、法律上のルールを守ることが極めて重要です。特に自筆証書遺言の場合、全文の自書、作成日の明記、署名、押印の4点が必須条件となります。一つでも欠けていると、遺言書全体の効力が認められない可能性があります。
また、遺産を受け取る相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。遺留分を侵害する内容の遺言は、後のトラブルに発展しかねません。自宅で保管する場合、死後に家庭裁判所の「検認」という手続きが必要になることも覚えておきましょう。
【2025年最新】おすすめの遺言書キット5選
遺言書を作成することで、大切なご家族にご自身の意思を正確に伝え、将来の相続トラブルを防ぐ助けとなります。しかし、どのキットを選べばよいか迷ってしまう方も多いでしょう。そこで今回は、数ある商品の中から特におすすめの遺言書キットを厳選してご紹介します。
初心者向けの使いやすさ、法的な要件への対応、付属品の充実度を基準に選びました。この記事を参考に、ご自身にぴったりの遺言書キットを見つけて、安心して遺言書作成の第一歩を踏み出してください。
コクヨ 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き
「コクヨ 遺言書キット」は、自筆証書遺言を簡単かつ法的に有効な形で作成できる初心者向けの人気商品です。遺言書作成の手順を丁寧にサポートする解説書や高品質な用紙がセットになっており、これ一つで安心して準備を始められます。
漫画付きの分かりやすい解説書
「遺言書虎の巻」という漫画付きの解説書が付属しており、法律の難しい内容も直感的に理解できるよう工夫されています。イラストを交えた丁寧な説明で、初めての方でもスムーズに作成を進めることが可能です。
高品質な用紙と改ざん防止機能
遺言書用紙にはコピーをすると「複写」の文字が浮き出る特殊な加工が施され、重要な書類の機密性が保たれます。また、厚手で書きやすい用紙は長期保存にも適しており、封筒も不正開封を防ぐ仕様でセキュリティ面も万全です。
保管用台紙で整理が簡単
専用の保管用台紙が付属しているため、作成した遺言書をきれいに整理して保管できます。立てて収納できる仕様で、本棚などにも収まりやすく、遺言書が傷ついたり紛失したりするリスクを軽減できるのが特徴です。
おすすめの方
- 遺言書を初めて作成する方
- 分かりやすい解説書を求めている方
- 安全に保管できる機能を重視する方
「コクヨ 遺言書キット」は、これから遺言書の準備を始めようと考えている方にとって、非常に頼りになるアイテムです。セット内容の充実度と使いやすさで、多くの方から高い評価を得ています。
遺言書作成キット
「遺言書作成キット」は、法務局の保管制度に対応した改ざん防止用紙や高級封筒が付属し、実用性と信頼性を兼ね備えた商品です。このキットを使えば、専門家に頼ることなく法的に有効な遺言書を簡単に作成できます。
自筆証書遺言書保管制度に対応
このキットは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度の様式に準拠しています。遺言書用紙は複写式で、1枚目を提出用、2枚目を控えとして手元に残せるため、コピーの手間を省きながら高い機密性を確保できます。
実例に基づく解説書
付属の解説書では、一般家庭で起こりがちな相続トラブルや、それを回避するためのポイントが実例を交えて丁寧に解説されています。ご自身の家族構成や財産状況に合った、具体的な遺言書を作成するためのヒントが得られます。
下書き用紙と申請書も付属
下書き用紙が付属しており、清書する前に遺言内容をじっくり整理するのに便利です。また、法務局へ提出する際の申請書も含まれているため、手続きをスムーズに進められる点も大きな魅力と言えるでしょう。
おすすめの方
- 法務局の保管制度を活用したい方
- 実例に基づいた具体的なアドバイスを求めている方
- 高品質な用紙で遺言書を作成・保管したい方
「遺言書作成キット」は、特に法務局の保管制度を利用したい方や、初めて遺言書を作成する方に最適です。実用的なセット内容と信頼性の高いサポートで、将来の安心を確保できるでしょう。
誰でも簡単につくれる遺言書キット
「誰でも簡単につくれる遺言書キット」は、遺言書の作成を手軽に始めたい方にぴったりのオールインワン商品です。近年の相続法改正や法務局の保管制度に対応しており、初心者でも安心して使える内容となっています。
基礎知識と実践ガイドの2冊セット
本キットには「遺言書の基礎知識ブック」と「遺言書の書き方ガイド」の2冊が含まれています。基礎知識ブックはマンガ形式で、法律やよくある疑問を分かりやすく解説。ガイドブックでは、具体的な記入例や訂正方法まで丁寧に説明されています。
法務局の保管制度に対応
このキットは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度に対応しています。付属の清書用紙は公式の様式を満たしており、作成後はスムーズに提出できます。これにより、遺言書の改ざんや紛失のリスクを防ぎ、家庭裁判所での検認も不要になります。
分かりやすい記入サポート
遺言書作成で重要なポイントを押さえた記入サポートも魅力です。例えば、配偶者や相続人との話し合いの進め方や財産目録の作成例など、初心者がつまずきやすい部分を丁寧に解説しており、トラブルを未然に防ぎながら確実な遺言書が作れます。
おすすめの方
- 初めて遺言書を作成する方
- 法務局の保管制度を利用したい方
- 具体的なガイド付きで進めたい方
「誰でも簡単につくれる遺言書キット」は、その名の通り、誰でも安心して始められる使いやすさが魅力です。専門知識に不安がある方でも、このキットなら問題なく利用できるでしょう。
これで困らない!自分でできる遺言書
「これで困らない!自分でできる遺言書」は、弁護士が監修した手引き書が付属した信頼性の高い遺言書作成キットです。2018年の民法改正に対応しており、最新の法制度に基づいた内容で、初めての方でも安心して遺言書を作成できます。
弁護士監修による分かりやすい解説
本書は弁護士による監修が行われており、法的な正確性が担保されています。遺言書作成時の注意点や相続トラブルを防ぐためのポイントを具体的に解説。どのような内容が書けるかなど、初心者にも分かりやすい言葉で説明されています。
基礎知識から実践までを網羅
このキットには、遺言書の基礎知識を学べる解説書と、実際の書き方を説明した手引き書が含まれています。財産目録の作成方法や遺言書の訂正手順までカバーしているため、これ一冊で作成に必要な情報をすべて得ることができます。
便利な作成用紙付き
付属の遺言書作成用紙は、法的な要件を満たせるよう工夫されています。清書用紙や封筒もセットになっているため、作成後の管理も簡単です。すぐに書き始められる手軽さも嬉しいポイントです。
おすすめの方
- 弁護士監修の信頼できる内容を求める方
- 基礎から実践までしっかり学びたい方
- 初めて遺言書を作成する方
「これで困らない!自分でできる遺言書」は、シンプルでありながら法的に有効な遺言書を作成できる優れたツールです。法律の知識に自信がない方でも、このキットを活用すれば安心して作業を進められるでしょう。
誰でも作れる遺言書 レッツ遺言セット
「誰でも作れる遺言書 レッツ遺言セット」は、神奈川県司法書士協同組合が監修した安心の遺言書作成キットです。約40年ぶりに見直された相続法改正に完全対応しており、初心者でも簡単に法的な要件を満たした遺言書を作成できます。
2018年の民法改正に対応した最新仕様
このキットは2018年の民法改正に対応しており、配偶者居住権の新設や自筆証書遺言の方式緩和といった新しい制度に基づいた遺言書作成が可能です。最新の法制度に沿った内容を簡単に反映できる点が大きな特徴です。
使いやすい便箋と封筒が付属
付録として、遺言書用の便箋(5通)や封筒(3通)、財産リスト(3枚)が含まれており、ペンさえあればすぐに遺言書作成を始められます。財産リストは、ご自身の財産状況を整理するのに役立ち、スムーズな作成をサポートします。
見本付きで安心
遺言書作成の見本が付属しているため、初めての方でも安心して書き進めることができます。具体的な記載例や注意点が明記されているので、重要なポイントを見逃す心配がなく、法的に有効な遺言書を完成させられます。
おすすめの方
- 最新の相続法に対応した遺言書を作成したい方
- 手軽に始められるキットを探している方
- 初めて遺言書を書く方
「誰でも作れる遺言書 レッツ遺言セット」は、初心者でも使いやすい設計でありながら、法律的に有効な遺言書を作成できる信頼性の高い商品です。相続にしっかりと備えたい方におすすめします。
遺言書キットの選び方|初心者が知っておくべき5つのポイント
遺言書キットを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。どのキットを選ぶかによって、作成の手軽さや法的な安心感が大きく変わるためです。特に初めて遺言書を作成する方は、分かりやすく有効なものを選ぶことが大切です。
以下では、初心者が知っておくべき選び方のポイントを5つに分けて解説します。それぞれのポイントを確認し、ご自身に最適な遺言書キットを選んで、スムーズに作成を進めましょう。
ポイント1:法律的に有効な遺言書が作れるか
遺言書を作成する上で最も重要なのは、その遺言書が法律的に有効であることです。自筆証書遺言の場合、ご自身の筆跡で全文を書き、日付と氏名を署名し、押印する必要があります。これらの要件が一つでも欠けると無効になる恐れがあります。
そのため、購入するキットがこれらの要件を満たすためのガイドや様式を提供しているかを確認しましょう。また、最新の法律(2018年の民法改正など)に対応しているかどうかも、信頼できるキットを見極める重要なポイントです。
ポイント2:セット内容が充実しているか
遺言書キットを選ぶ際は、セット内容が充実しているものを選びましょう。専用の用紙や封筒だけでなく、詳しい解説書や具体的な文例集が含まれていると、初心者でも安心して作成を進められます。下書き用紙の有無も確認するとよいでしょう。
さらに、保管用のファイルやケースが付属していると、完成した遺言書を安全に管理するのに役立ちます。購入前に、ご自身が必要とするものが一式揃っているかを確認することが、スムーズな作成への近道です。
ポイント3:解説書の分かりやすさとサポートの有無
初めて遺言書を作成する方にとって、分かりやすい解説書があることは非常に重要です。法律用語が少なく、図やイラストで説明されているものを選ぶと、内容を理解しやすくなります。書き方の見本が具体的であるかもチェックしましょう。
また、一部のキットには電話やオンラインでの質問サポートが付いているものもあります。作成中に生じた疑問点を専門家に相談できるため、より安心して遺言書を完成させたい方には心強いサービスです。
ポイント4:口コミや評判を参考にする
実際にそのキットを使用した人の意見は、選ぶ際の有力な情報源になります。公式サイトの商品説明だけでなく、ECサイトのレビューや個人のブログなどで、他の利用者の体験談を調べてみましょう。
特に、「解説書の分かりやすさ」「用紙の質」「付属品の使いやすさ」についての評価が高いものを選ぶと失敗しにくくなります。複数の情報を参考にして、総合的に判断することが大切です。
ポイント5:予算に合った価格帯を選ぶ
遺言書キットの価格は、数千円程度のものから一万円を超えるものまで様々です。まずはご自身の予算に合ったものを選ぶことが大切ですが、安さだけで決めず、内容の充実度とのバランスを考慮しましょう。
一般的に、価格が高いキットは弁護士などの専門家が監修していたり、サポートが手厚かったりする傾向があります。ご自身の知識レベルや求める安心感に合わせて、最適な価格帯のキットを選びましょう。
遺言書キットを使った遺言書の書き方ガイド
遺言書を作成することは、ご家族や大切な人へご自身の想いを形として残す重要な行為です。しかし、多くの方が「何から始めればいいのか分からない」と感じています。そこで活躍するのが遺言書キットであり、初めての方でも手軽に作成できるよう設計されています。
このガイドでは、遺言書キットを使った具体的な書き方の手順や、トラブルを防ぐための注意点を解説します。さらに、作成後の正しい保管方法や、家庭裁判所での手続きについても触れていきますので、自信を持って遺言書を完成させましょう。
遺言書キットを使った具体的な作成手順
遺言書キットを使った作成手順は非常にシンプルです。まず、キットに付属している説明書をよく読み、全体の流れを把握しましょう。次に、財産目録などを作成し、誰に何を相続させるかを下書き用紙に整理していきます。
内容が固まったら、清書用の用紙にボールペンなどで丁寧に書き写します。最後に、必ず作成した日付を記入し、署名と押印をしてください。完成したらキット付属の封筒に入れ、しっかりと封をして保管します。
トラブルを防ぐための記載例と注意事項
相続トラブルを防ぐためには、遺言書の内容を明確に記載することが重要です。「誰に」「どの財産を」「どれくらい」相続させるのかを具体的に書きましょう。曖昧な表現は、解釈をめぐる争いの原因になるため避けるべきです。
例えば、「長男〇〇に、〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号12345)の全てを相続させる」のように具体的に記載します。また、法定相続人以外の人物に財産を遺す場合は、その理由を付記しておくと、他の相続人の理解を得やすくなります。
完成した遺言書の保管方法
完成した遺言書は、安全な場所に保管することが大切です。自宅で保管する場合は、紛失や盗難、火災などのリスクを考慮し、耐火金庫などに入れると安心です。また、遺言書の存在と保管場所を、信頼できる家族や遺言執行者に伝えておきましょう。
より確実な方法として、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することもおすすめです。この制度を使えば、紛失や改ざんのリスクを防げるうえ、死後の家庭裁判所での検認手続きが不要になるという大きなメリットがあります。
遺言書の提出と家庭裁判所での手続き
自筆証書遺言を自宅などで保管した場合、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。これは遺言書の偽造や変造を防ぎ、内容を相続人全員に知らせるための手続きです。
まず、相続人の一人が家庭裁判所に遺言書と検認申立書を提出します。その後、裁判所が指定した期日に相続人全員が集まり、裁判官の立ち会いのもとで遺言書が開封されます。検認を経ることで、遺言書に基づいて不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを進められるようになります。
遺言書キットはこんな人におすすめ
遺言書キットは、人生の節目にご自身の意思を形として残すための便利なツールです。「まだ早い」と感じる方もいるかもしれませんが、遺言書を準備しておくことは、ご自身とご家族の将来の安心につながります。特に、終活を考えている方や、家族関係を大切にしたい方におすすめです。
以下では、どのような方に遺言書キットが役立つのか、具体的なケースをご紹介します。それぞれの状況に応じた使い方を知ることで、キットをより効果的に活用できるはずです。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
終活を始めた方
終活を始めると、ご自身の人生を整理し、未来に備える意識が高まります。その中で多くの方が直面するのが、「財産をどう分けるか」という課題です。遺言書キットは、この課題をシンプルに解決するための強力なツールとなります。
キットには必要な書類やガイドが含まれており、専門知識がなくても手軽に始められます。終活の一環として財産の分け方を明確にすることで、ご家族が将来抱える負担を大きく軽減できます。また、ご自身の意思を形に残せる安心感も得られるでしょう。
相続トラブルを未然に防ぎたい方
相続をめぐるトラブルは、時として家族間の深刻な対立を引き起こす原因となります。「財産をどう分けるか」で意見が食い違い、関係が悪化するケースは少なくありません。こうしたトラブルを未然に防ぐために、遺言書キットの活用は非常に有効です。
明確な遺言書を用意することで、財産分割の指針が示され、相続人間の争いを防ぐことができます。遺言書キットを使えば、法的に有効な形式で遺言書を作成できるため、ご家族の平和を守るための重要な役割を果たします。
ご家族にご自身の意思をしっかり伝えたい方
遺言書は、単なる財産分割の指示書ではありません。ご自身の想いや感謝の気持ちをご家族に伝えるための、大切なメッセージツールとしても活用できます。普段はなかなか口に出して言えない言葉を、遺言書に託してみてはいかがでしょうか。
例えば、「この家を長男に譲るのは、家族の思い出を守ってほしいから」といった理由や、「これまでありがとう」という感謝の言葉を書き添えることができます。遺言書キットを使えば、法的な要件を満たしつつ、心のこもったメッセージを残すことが可能です。
まとめ
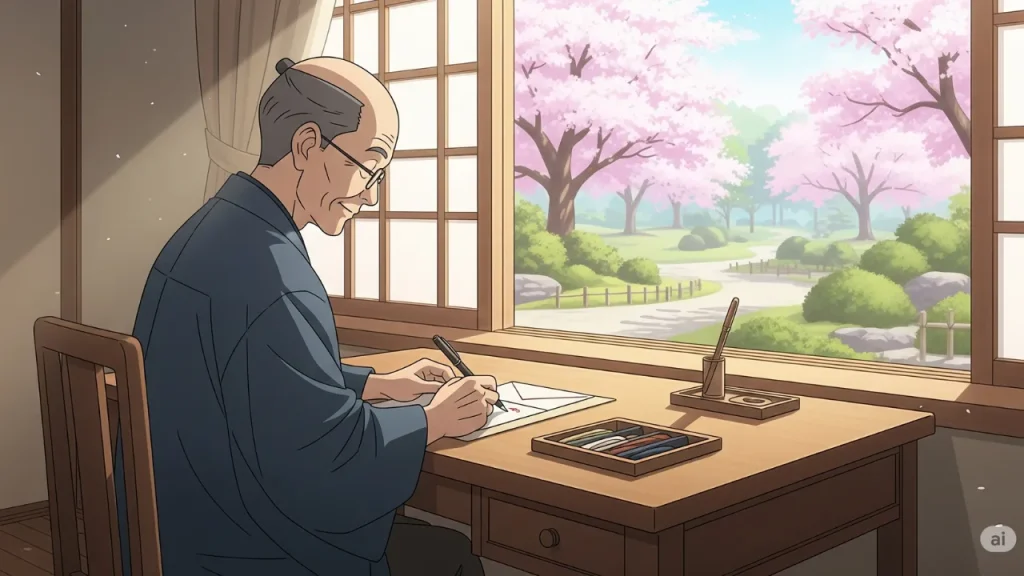
この記事では、遺言書作成に役立つおすすめの遺言書キットをご紹介しました。それぞれのキットの特徴や魅力を詳しく解説し、初心者でも選びやすいようにまとめています。ご自身に合ったキットは見つかりましたでしょうか。
遺言書キットを使えば、専門知識がなくても法的に有効な遺言書を簡単に作成できます。また、今回ご紹介した選び方のポイントや書き方のガイドを押さえれば、スムーズに作成を進めることが可能です。
あなたに合った遺言書キットを選び、未来の安心を手に入れる準備を始めましょう。遺言書の作成は、ご家族への想いを形にする大切な一歩です。この記事を参考に、ぜひ行動を起こしてみてください。