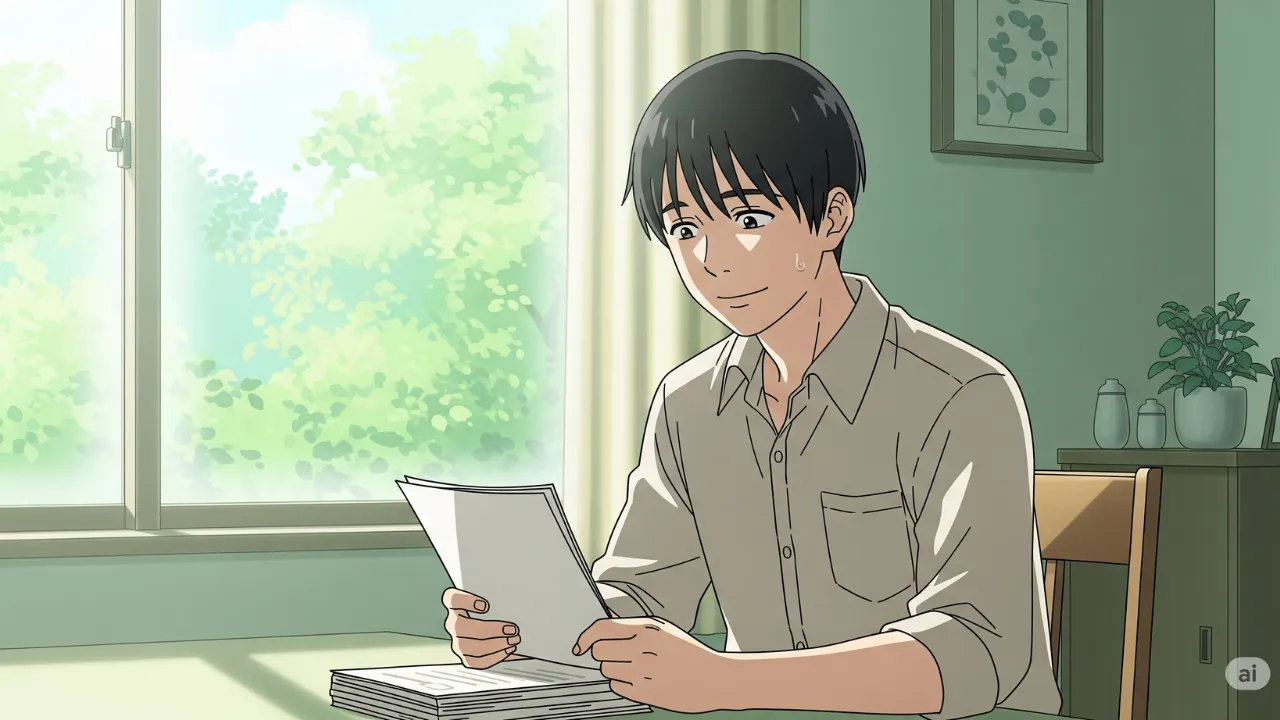はじめに:介護で働けない…経済的な不安を抱えていませんか?
ご家族や親の介護が必要になり、これまで通りに働くことが難しくなったと感じていませんか。「介護のために仕事を休まざるを得ない」「収入が減ってしまい、これからの生活が不安だ」といった悩みは、多くの方が抱えている現状です。
しかし、追い詰められた気持ちになる前に、利用できる公的な支援制度があることを知ってください。国や自治体は、介護を担う方の経済的負担を軽減するための補助金や給付金、各種制度を用意しています。この記事では、介護で働けないあなたの状況に合わせて活用できる支援制度を網羅的に解説します。正しい知識を得て、経済的な不安を少しでも和らげましょう。
【状況別】介護で働けない時に使える公的支援制度の種類
介護で働けないといっても、その状況は人それぞれです。「一時的に休業している」「やむを得ず離職した」「すでに収入がほとんどない」など、ご自身の状況に近いものから読み進めてみてください。
ここでは、これから解説する支援制度を3つの状況に分けてご紹介します。それぞれ対象となる制度が異なりますので、ご自身の状況に合ったものを確認することが大切です。
仕事を休業して介護する場合に使える制度
現在の仕事を続けながら、一時的に休んで介護に専念したい場合に活用できる支援制度です。雇用保険に加入している方が主な対象となります。
介護離職を防ぐための重要な選択肢であり、まず最初に検討すべき制度といえるでしょう。主な制度として介護休業給付金があります。
介護を理由に離職した場合に使える制度
残念ながら介護のために仕事を辞めざるを得なかった場合に、次の仕事を見つけるまでの生活を支える支援制度です。雇用保険の制度が中心となります。
単なる自己都合退職とは異なる扱いを受けられる可能性があるため、必ず確認しておきましょう。主な制度として失業保険(雇用保険の基本手当)があります。
収入が著しく低い・ない場合に検討する制度
すでに離職しており、貯蓄も尽きかけているなど、生活自体が困難な状況に陥った場合の最後のセーフティネットです。資産や収入に関する一定の条件がありますが、憲法で保障された制度です。
健康で文化的な最低限度の生活を守るための大切な制度として、生活保護があります。適切な利用を検討しましょう。
介護離職を防ぐための第一歩「介護休業給付金」
介護休業給付金は、労働者が要介護状態にある家族を介護するために仕事を休業した場合に、その間の収入を支える目的で支給される給付金です。仕事と介護の両立を支援し、安易な介護離職を防ぐための非常に重要な制度となります。
雇用を継続したまま介護に専念できる期間を確保できるため、まずはこの制度の活用を検討しましょう。詳しくは勤務先やハローワークに確認することをおすすめします。
介護休業給付金の対象者となる主な条件
この給付金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。基本的な条件は以下の通りですが、詳細は勤務先やハローワークにご確認ください。
対象者の条件を事前に把握し、適切な準備を整えることが重要です。不明な点があれば、遠慮なく専門機関にお問い合わせください。
- 雇用保険の被保険者であること。
- 介護休業開始日の前2年間に雇用保険に加入している期間が12カ月以上あること。
- 対象家族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹など)が、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態であること。
- 介護休業後に復職する予定であること。
支給額と期間の目安について
支給される金額は、休業開始前の賃金を基に算出されます。具体的な金額は個々の状況によって異なりますが、休業中の収入を補う大きな助けとなるでしょう。
支給を受けられる期間は、対象家族1人につき通算93日までとなっており、最大3回まで分割して取得することが可能です。これにより、状況に応じて柔軟に休業計画を立てられます。
申請手続きの流れと注意点
一回の介護休業終了後、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。申請は原則として勤務先の事業主を通じて行われます。
申請には期限が設けられているため、介護休業を取得する意思が固まったら、速やかに会社の担当部署(人事部など)に相談することが重要です。介護対象家族の状況を証明する書類なども必要になる場合がありますので、早めに準備を始めましょう。
やむを得ず離職した後の生活を支える「失業保険(特定理由離職者)」
様々な事情から介護休業制度を利用できず、やむを得ず離職を選択した場合、次の生活の目処が立つまでの支えとなるのが雇用保険の「基本手当」、いわゆる失業保険です。特に、親の介護など家庭の事情が急変したことによる離職は、「特定理由離職者」として認められる可能性があり、一般の自己都合退職よりも手厚い給付を受けられる場合があります。
介護で働けない状況で離職せざるを得ない場合、この制度の活用を検討することで、経済的な不安を軽減しながら再就職活動に臨むことができます。
「特定理由離職者」とは?自己都合退職との違い
「特定理由離職者」とは、自己都合ではあるものの、離職するにあたって正当な理由があったと認められる人のことを指します。親の介護のために離職せざるを得なかった場合、この区分に認定されることがあります。
認定されると、通常3ヶ月かかる給付制限期間がなく、すぐに失業手当の受給を開始できるという大きなメリットがあります。介護で働けない状況にある方にとって重要な制度です。
給付日数や金額面での優遇
特定理由離職者と認定された場合、失業手当を受けられる給付日数も長くなる場合があります。受給できる日数は、年齢や雇用保険の被保険者であった期間によって決まります。
支給される金額は離職前の賃金に基づいて計算されますが、給付日数が延びることで、より長く経済的な支援を受けながら再就職活動に専念できます。
ハローワークでの手続き方法
失業保険を受給するための手続きは、ご自身の住所地を管轄するハローワークで行います。手続きには、会社から交付される「離職票」やマイナンバーカード、写真などが必要です。
介護が理由で離職したことを証明するために、介護の事実がわかる客観的な資料の提出を求められることがありますので、事前にハローワークに必要書類を確認しておくとスムーズです。
在宅介護の経済的負担を軽くする介護保険の制度
直接的な現金給付ではありませんが、在宅介護を続ける上での経済的負担を大きく軽減してくれるのが「介護保険」の各種制度です。介護サービスの利用にかかる費用は家計にとって大きな負担となりがちですが、これらの制度をうまく活用することで、支出を抑えることが可能です。
見落としがちな制度も多いため、ぜひ確認してください。介護保険サービスを最大限に活用し、介護生活を安定させましょう。
高額なサービス費の一部が戻る「高額介護サービス費」
「高額介護サービス費」は、1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額の合計が上限額を超えた場合に、その超えた分の金額が払い戻される制度です。申請をしないと払い戻しは受けられませんので、お住まいの市区町村の窓口で手続きが必要です。
特に、複数の介護サービスを利用している場合は、自己負担額が高額になりやすいので注意しましょう。高額な医療費や介護費用を軽減する制度について、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
自治体が独自に行う「家族介護慰労金」とは
国の制度とは別に、市区町村が独自に実施している支援制度に「家族介護慰労金」があります。これは、在宅で重度の要介護者を介護している家族に対して、その労をねぎらう目的で慰労金や手当を支給するものです。
対象となる要介護度や同居の有無、介護期間などの条件は自治体によって大きく異なります。お住まいの市区町村の高齢福祉課などに問い合わせてみましょう。
おむつ代の助成など市町村独自の支援も確認
慰労金の他にも、自治体によっては在宅介護者を支援するための様々な取り組みがあります。代表的なものに、紙おむつなどの介護用品の購入費用を助成する制度や、現物を支給する制度があります。
他にも、自宅への訪問理美容サービスの費用助成など、地域の実情に応じた支援が存在します。これらも貴重な家計の助けとなりますので、積極的に情報を集めてみてください。
最終的なセーフティネットとしての「生活保護」
他のどの制度も利用できない、あるいは利用してもなお生活が困窮し、最低限度の生活を維持することが困難な場合には、「生活保護」の活用を検討します。これは国民の権利として定められた制度であり、ためらう必要はありません。
親の介護で働けないという状況も、受給のための正当な理由として認められる可能性があります。まずは福祉事務所に相談し、ご自身の状況について詳しく説明してみましょう。
生活保護を受給するための要件
生活保護を受給するには、以下の要件が総合的に判断されます。親が年金を受給していても、世帯全体の収入が最低生活費を下回る場合は対象となる可能性があります。
各要件について詳しく確認し、自分の状況に該当するかを正確に把握することが重要です。まずは福祉事務所に相談してみましょう。
- 世帯全体の収入が最低生活費に満たないこと。
- 活用できる資産(預貯金、生命保険、不動産、自動車など)がないこと。
- 働く能力がある場合は、その能力を活用していること。(※介護の場合は働けない理由として考慮されます)
- 親族などから援助を受けられないこと。
介護サービス費用も対象になる「介護扶助」
生活保護制度には、生活を営む上で必要な費用を賄うための8種類の「扶助」があります。その中の一つである「介護扶助」により、介護保険サービスの1割自己負担分や、介護保険料などが原則として全額支給されます。
これにより、経済的な心配をすることなく、必要な介護サービスを利用することができます。適切なケアを受けながら生活を維持できる重要な制度です。
相談・申請の窓口と知っておくべきこと
生活保護の相談・申請は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所の「生活保護担当窓口」で行います。申請は本人のほか、家族や親族も行うことができます。
相談したからといって、必ず申請しなければならないわけではありません。まずは現状を正直に話し、どのような支援が受けられる可能性があるかを確認することから始めましょう。地域包括支援センターへの相談も、最初の一歩としておすすめです。
【見落としがち】税金の負担を軽減する控除制度
補助金や給付金のように直接お金を受け取るものではありませんが、税金の負担を軽くすることも家計を助ける上で非常に重要です。親の介護をしている場合、年末調整や確定申告で手続きをすることで、所得税や住民税が安くなる「所得控除」を受けられる場合があります。
これらの制度は家計を助ける有効な手段となりますので、忘れずに活用しましょう。ご自身の状況に合わせて、利用可能な控除制度を確認してみてください。
親を扶養に入れることで適用される「扶養控除」
納税者が生計を同じくする親族を養っている場合に受けられるのが「扶養控除」です。親の年間の合計所得金額が一定の基準額以下であるなどの条件を満たせば、ご自身の扶養親族とすることができます。
これにより、あなたの所得税や住民税の負担が軽減されます。特に、70歳以上の親を扶養する場合は控除額が大きくなりますので、ぜひ確認しましょう。
要介護認定で対象になる場合がある「障害者控除」
ご自身、または扶養している親が税法上の障害者に該当する場合、「障害者控除」が適用され、税金の負担がさらに軽減されます。身体障害者手帳などを持っていなくても、要介護認定を受けている65歳以上の方については、市区町村長から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、控除の対象となる場合があります。
この制度は見落としやすいため、該当する可能性がある場合は積極的に確認してください。税務署や市区町村の税務担当窓口で詳しい説明を受けることができます。
まとめ:一人で抱え込まず、まずは専門機関に相談しましょう
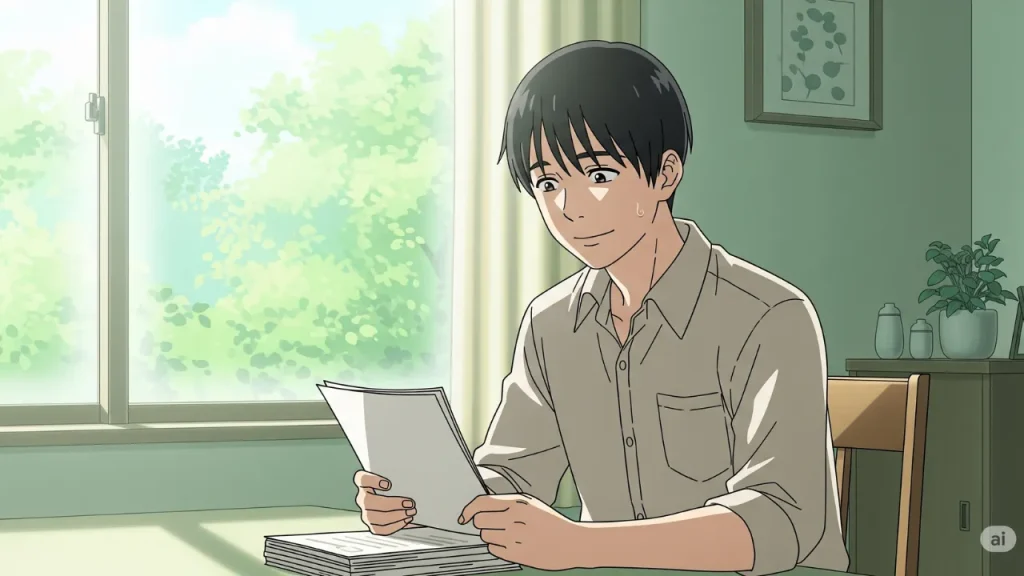
この記事では、介護で働けない状況になった際に活用できる様々な公的支援制度をご紹介しました。「介護休業給付金」で離職を防ぐ道を探ったり、やむを得ず離職した後は「失業保険」で生活を支えたりと、状況に応じた選択肢があります。介護離職を考え始めたら読む記事や、介護施設に関する金銭的サポートについて、ぜひ詳細をご確認ください。
また、「高額介護サービス費」や「家族介護慰労金」で日々の負担を減らし、最終的には「生活保護」というセーフティネットも存在します。介護保険の申請ガイドも役立つでしょう。最も大切なのは、悩みを一人で抱え込まず、できるだけ早く専門の機関に相談することです。お住まいの「地域包括支援センター」や、担当の「ケアマネージャー」、市区町村の「高齢福祉課」や「社会福祉協議会」などが、あなたの力になってくれるはずです。勇気を出して、まずは一本の電話から始めてみてください。
介護と補助金に関するよくある質問
ここでは、介護とお金に関するよくある質問とその答えをまとめました。多くの方が疑問に思う点ですので、ぜひ参考にしてください。
ご自身の状況に近い質問があれば、回答を確認することで、制度への理解を深めることができるでしょう。
家族の介護で国や自治体から直接もらえるお金はありますか?
A. はい、状況に応じていくつかの制度があります。仕事を休業する場合は雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。また、一部の自治体では、在宅で高齢者を介護する家族に対し「家族介護慰労金」などを支給している場合があります。ただし、いずれも受給には一定の条件があり、ご自身での申請が必要です。
親の介護を理由に離職した場合、失業保険は有利になりますか?
A. はい、「正当な理由のある自己都合退職」とみなされ、「特定理由離職者」として認定されることで、一般の自己都合退職に比べて有利になる可能性があります。具体的には、給付金を受け取るまでの待期期間が短縮されたり、給付を受けられる日数が長くなったりするメリットがあります。手続きはハローワークで行います。
介護で働けず収入がない場合、生活保護は受けられますか?
A. はい、受けられる可能性があります。生活保護は、資産や能力などあらゆるものを活用してもなお生活が困窮する場合に、最低限度の生活を保障する制度です。「親の介護のために働けない」という理由は、受給のための正当な理由として認められるケースが多くあります。まずはお住まいの地域を管轄する福祉事務所にご相談ください。
介護休業給付金は、どのくらいの金額がもらえますか?
A. 具体的な金額は個人の給与によって異なりますが、休業を開始する前の賃金日額に支給日数を乗じた額の一定の割合が支給されます。上限額も定められています。正確な見込み額については、勤務先の人事労務担当者や、管轄のハローワークに問い合わせて確認することをおすすめします。