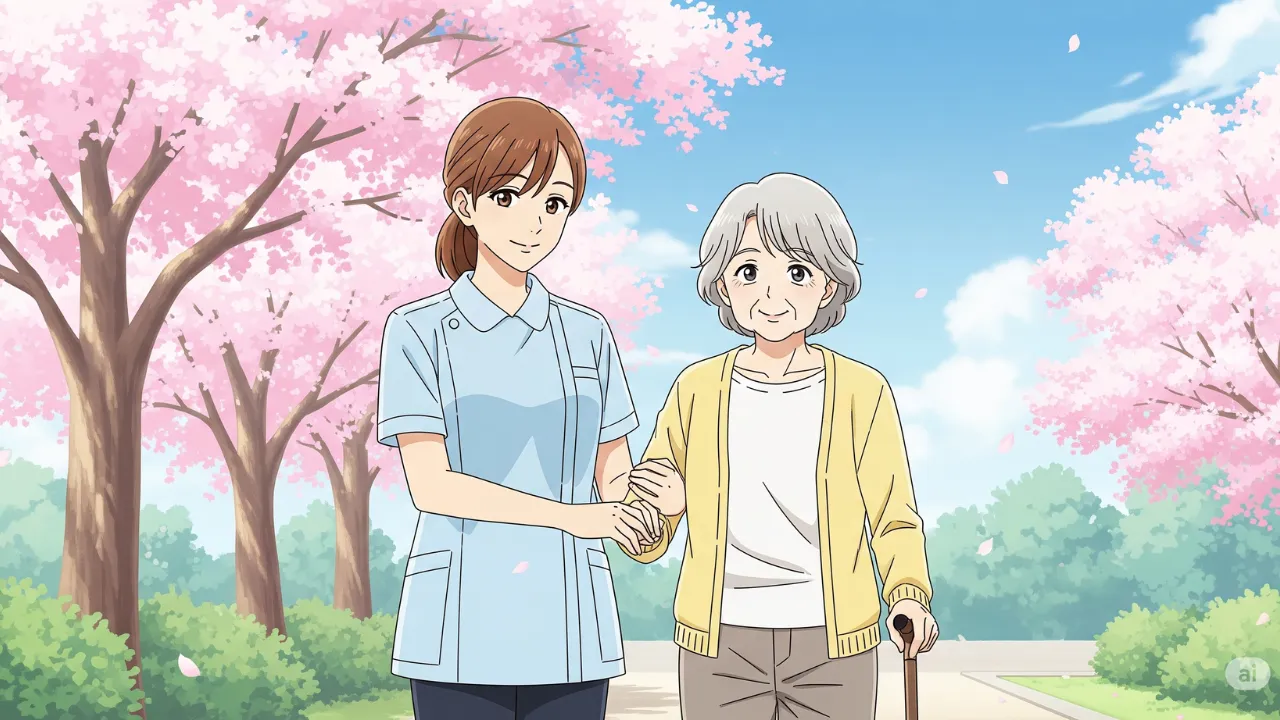はじめに:「徘徊」という言葉、使っていませんか?
ご家族の介護や職場で、認知症の方の行動に対して「徘徊」という言葉を何気なく使っていませんか。近年、この「徘徊」という言葉が持つニュアンスが見直され、言い換えの動きが急速に広がっています。言葉一つで、ご本人やご家族との関係、さらにはケアの質まで変わる可能性があるとしたら、どうでしょうか。
この記事では、なぜ「徘徊」の言い換えが必要なのか、その背景にある理由から、厚生労働省の見解、そして今日からすぐに使える具体的な言い換え表現まで、分かりやすく解説します。言葉の選び方に悩むあなたの疑問を解消し、より良いコミュニケーションへの第一歩を後押しします。
その言葉、相手を傷つけているかも
「徘徊(はいかい)」という言葉には、「目的もなく、あてもなくさまよう」という意味合いが含まれています。しかし、認知症の方の行動の多くには、ご本人なりの理由や目的が存在するのです。例えば、「家に帰りたい」「トイレを探している」といった切実な思いが行動に表れていることもあります。
「徘徊」と一括りにしてしまうことは、そうした本人の意思を無視し、尊厳を傷つけてしまう可能性があります。無意識に使ったその一言が、相手に深い孤独感や疎外感を与えているのかもしれません。
この記事でわかること
この記事を読めば、「徘徊」という言葉を巡る様々な疑問が解消されます。具体的には、以下の点が明らかになるでしょう。
- 「徘徊」という言葉の本来の意味となぜ言い換えが必要なのか
- 厚生労働省や自治体が推奨する新しい表現
- 介護の状況に応じた具体的な言い換えの言葉
- 言葉を変えた先にある、本人への適切な対応方法
これらの知識を得ることで、自信を持って適切な言葉を選び、ご本人に寄り添ったケアを実践できるようになります。
そもそも「徘徊」とは?言葉が持つ本来の意味と印象
「徘徊」の言い換えを考える前に、まずはこの言葉が本来持つ意味と、特に介護の現場でどのような印象を与えてきたのかを理解しておくことが重要です。言葉の背景を知ることで、なぜ言い換えが必要なのかがより深く見えてきます。
古くから使われてきた日本語ですが、その使われ方が時代と共に変化し、新たな課題を生んでいるのが現状です。
辞書が示す「徘徊」の定義
辞書で「徘徊」を調べると、「目的もなく、あちこちをうろうろと歩きまわること」といった意味が記載されています。この「目的もなく」という部分が、特に大きなポイントです。
言葉の本来の意味が、本人の意思や目的を想定していない、という点をまずは押さえておきましょう。この定義が、認知症の方の行動を説明する際に、誤解や偏見を生む一因となってきたと考えられます。
介護現場で使われる「徘徊」が与えるネガティブな印象
介護の現場では、徘徊は認知症高齢者によく起きる行動のひとつで、BPSD(周辺症状)の一つであり、記憶障害が原因となって引き起こされることがあります。しかし、この言葉はご本人の行動を問題行動として捉え、否定的なニュアンスを強く含んでいると言えるでしょう。
介護者が「徘徊」という言葉を使うことで、無意識のうちに「目的のない困った行動」というレッテルを貼ってしまう可能性があります。これにより、ご本人がなぜそのような行動をとるのか、その理由や背景を深く理解しようとする視点が妨げられることもありました。
なぜ今「徘徊」の言い換えが必要?介護現場で進む3つの理由
「徘徊」という言葉からの転換は、単なる言葉狩りではありません。そこには、ご本人への敬意を払い、ケアの質を向上させようとする明確な意図が存在します。
ここでは、なぜ今、介護の現場を中心に「徘徊」の言い換えが必要とされているのか、その主な3つの理由を解説します。この動きは、より良い介護環境を築くための重要なステップなのです。
理由1:本人の尊厳を守り、無用な偏見をなくすため
最も大きな理由は、ご本人の尊厳を守るためです。前述の通り、「徘徊」は本人の意思を軽視した表現であり、時に差別用語と受け取られることもあります。
言葉が変われば、当事者や周囲の認識も変わります。例えば「徘徊老人」という表現は、その人個人ではなく記号として見てしまう偏見を助長しかねません。言葉遣いを改めることは、一人の人間として尊重する姿勢を示す第一歩です。
理由2:目的のある「行動」であるという認識を広めるため
認知症の方の「徘徊」と見える行動は、実は本人にとって目的のある「行動」であることが多いです。記憶障害などにより、その目的が周囲に伝わりにくいだけなのです。
- 帰宅願望:ここが自分の家だと認識できず、慣れ親しんだ自宅に帰ろうとする。
- 過去の習慣:「会社へ行く」「子供を迎えに行く」など、過去の習慣を思い出して行動する。
- 生理的欲求:トイレの場所が分からず探している。
- 不快感の解消:騒音や暑さ・寒さなど、不快な環境から逃れようとしている。
「徘徊」ではなく「行動」と捉えることで、その裏にある原因を探り、不安や混乱を取り除く支援につなげることができます。
理由3:厚生労働省や自治体による方針転換
個人の意識だけでなく、国や自治体レベルでも「徘徊」という言葉を見直す動きが広がっています。厚生労働省は公式な通知や資料において「徘徊」という言葉を使わず、主に「ひとり歩き」という表現を用いています。
多くの自治体でも言い換えの取り組みが進んでおり、社会全体の認識を変える大きな力となっています。介護サービスを提供する側も、こうした社会的な流れを汲み取り、適切な表現を用いることが強く求められます。
厚生労働省が示す「徘徊」の言い換え方針「ひとり歩き」とは
「徘徊」に代わる言葉として、現在最も広く使われ始めているのが「ひとり歩き」という表現です。この言葉は、厚生労働省が中心となって推奨しており、多くの自治体や介護現場で浸透しつつあります。
では、なぜ「ひとり歩き」という言葉が選ばれたのでしょうか。その背景にある意味を理解していくことが大切です。
「ひとり歩き」に込められた意味と背景
「ひとり歩き」という言葉は、「本人の意思で一人で歩いて外出している」という主体性を尊重した表現です。これは「目的もなくさまよう」という意味合いを持つ「徘徊」とは対照的です。
この言葉を使うことで、支援する側も「何か目的があって外出したのかもしれない」という視点を持ちやすくなります。結果として、ご本人の気持ちに寄り添い、行動の理由を探る、質の高いケアにつながることが期待されています。
【事例】全国の自治体で進む言い換えの取り組み
厚生労働省の方針を受け、全国の自治体で言い換えの取り組みが具体的に進んでいます。例えば、愛知県大府市など、多くの自治体が「徘徊」を「ひとり歩き」と表現するように変更しています。
また、「行方不明者」「認知症」といった言葉に言い換える例も多いです。これらの取り組みは、地域全体で高齢者を見守る地域包括ケアシステムの推進と連動しています。
【状況別】「徘徊」の言い換え表現集と使い分けのポイント
「徘徊」の代替表現は「ひとり歩き」だけではありません。状況や相手の様子に応じて言葉を使い分けることで、より的確に、そして思いやりを持ってコミュニケーションをとることができます。
ここでは、具体的な状況別に使える言い換え表現をいくつか紹介します。大切なのは、目の前の人の状態をよく観察し、適切な言葉を選ぶことです。
認知症の方の外出を示す場合:「ひとり歩き」「お散歩」など
ご本人が一人で外出されたり、外出しようとされたりする場面では、「ひとり歩き」や「お出かけ」「お散歩」といった、より前向きで自然な言葉を選ぶのが良いでしょう。
ご家族や介護者同士で情報を共有する際に、「〇〇さんがおひとりで外出されました」と表現することで、否定的なニュアンスなく事実を伝えられます。ご本人に声をかける際も、自然に会話を始めるきっかけになります。
不安や混乱から動いている様子の言い換え:「落ち着かないご様子」
家の中や施設内を目的なく歩き回っているように見える時、それは不安や混乱、あるいは身体的な不快感のサインかもしれません。このような場合は、「徘徊している」と決めつけるのではなく、「落ち着かないご様子ですね」といった表現が適切です。
これは、相手の行動を評価するのではなく、その時の状態を描写し、気遣う言葉です。介護記録などでもこのように記載することで、他の職員も本人の心情を考慮したケアを意識しやすくなるでしょう。
若者や目的のない外出の言い換え:「夜間のそぞろ歩き」など
「徘徊」は高齢者だけに使う言葉ではありません。例えば若者が深夜に特に目的もなく歩き回ることを「深夜徘徊」と表現することがありますが、これもまた、ネガティブな印象を与えがちです。
ストレス解消や気分転換など、本人なりの理由がある場合も多いでしょう。このような場合は、「夜の散策」や「夜間のそぞろ歩き」といった、より情緒的な表現を使うことができます。
言葉を変えることで、補導や非行といった問題行動のイメージから切り離し、個人の自由な時間として捉えることが可能となります。
言葉だけでなく行動の背景を理解する視点が重要
最も大切なのは、単に言葉を置き換えることではありません。なぜその人は歩き回っているのか、その行動の背景にある気持ちや理由を理解しようと努める姿勢が重要です。
言葉は、私たちの思考や認識を形作ります。「徘徊」という言葉を使うのをやめることは、相手を深く理解するための第一歩です。常に、行動の裏にある「声」に耳を傾ける視点を忘れないようにしましょう。
言葉を変えた先にあるもの:「ひとり歩き」への適切な対応策
「徘徊」を「ひとり歩き」と言い換えることは、本人理解の始まりに過ぎません。言葉を変え、認識を新たにした上で、次に行うべきは具体的な対応です。
ご本人の安全を守り、不安を和らげるためには、どのような対策や心構えが必要なのでしょうか。ここでは、言葉の先にある実践的な対応策について解説します。
まずは本人の安全を確保する
「ひとり歩き」で最も懸念されるのは、交通事故や転倒、天候による体調不良などの危険です。ご本人の命に関わるリスクを避けるため、安全の確保が最優先事項となります。
玄関にセンサーを設置して外出を知らせる、近所の方や地域の商店に見守りを依頼しておく、といった環境づくりが重要です。また、本人の尊厳を損なわない範囲で、目を離さずにいられる時間を確保するなど、介護者の体制を整える必要もあります。
なぜ外に出たいのか?5つの主な理由と気持ちの汲み取り方
安全を確保した上で、なぜご本人が「ひとり歩き」をするのか、その理由を探ることが大切です。頭ごなしに止めようとすると、かえって不安や混乱を招きます。
例えば、以下のような理由が考えられます。ご本人の言葉や表情から気持ちを汲み取り、共感する姿勢が安心につながることも多いです。
- 帰宅願望:「お家に帰られるのですね」と一度受け止め、一緒にお茶を飲むなどして気持ちを落ち着かせる。
- 役割の遂行:「会社ですか?お疲れ様です」と共感し、別の役割(洗濯物をたたむ等)をお願いしてみる。
- 生理的欲求:トイレに誘導したり、水分補給を促したりする。
- 不快感:室温を調整したり、静かな場所に移動したりする。
- 習慣:日課だった散歩の時間であれば、一緒に出かける。
GPSや見守りサービスなど事前の備えで安心を
万が一、ご本人が行方不明になった場合に備えて、事前の対策を講じておくことは家族の安心につながります。小型のGPSトラッカーなどを靴やカバンに付けておくと良いでしょう。
スマートフォンなどから現在地を確認できるGPS靴などの見守りサービスが普及しています。高齢者見守りサービスを比較し、適切なものを選びましょう。
また、自治体によっては、行方不明者の情報をメールで配信する制度や、発見・保護に協力した市民に感謝状を贈る制度(例:おかえりなさい支援事業)などを実施しています。
お住まいの地域の高齢者見守りや遠隔見守りサービスを確認してみましょう。
まとめ:「徘徊」の言い換えは、本人理解とより良いケアの第一歩
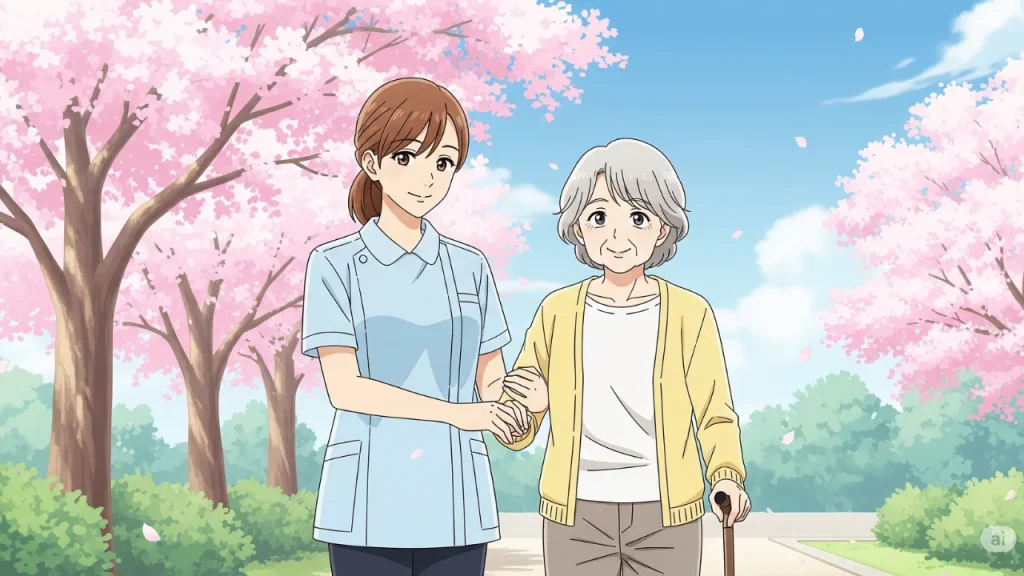
「徘徊」という一つの言葉を見直すことは、私たちが認知症の方々とどう向き合うかという、より大きな問いにつながっています。「徘徊」を「ひとり歩き」に変えることは、認識の転換と言えるでしょう。
単なる言葉の変更ではなく、相手を「意思のある一人の人間」として捉え直します。この小さな一歩が、ご本人の尊厳を守り、行動の裏にある真の理由を探るきっかけとなるでしょう。
そして、その理解が、より質の高い、心に寄り添ったケアを実現させるのです。この記事が、あなたの言葉選びの指針となり、大切な人とのより良い関係を築く一助となれば幸いです。
「徘徊の言い換え」に関するよくある質問
「徘徊」という言葉は差別用語にあたりますか?
法律などで明確に差別用語と定義されているわけではありません。しかし、「目的もなくさまよう」という言葉の持つ否定的な意味合いが、本人の意思や尊厳を軽視し、誤解や偏見を助長する可能性があります。
そのため、多くの専門家や団体が使用を避けるべきだと考えています。特に介護や医療の現場では、より中立的で尊重のある言葉を選ぶのが現在の主流となっています。
厚生労働省は「徘徊」を何と言い換えていますか?
厚生労働省は、公式な通知や資料において「徘徊」という言葉を使わず、主に「ひとり歩き」という表現を用いています。
これは、認知症の方の行動をご本人の意思に基づくものとして捉え、その主体性を尊重する姿勢を示すためです。この方針は、多くの自治体や介護関連団体にも広まっています。
認知症の方が外に出てしまう心理的な原因は何ですか?
原因は一人ひとり異なり、一つに特定することは難しいですが、主に以下のような心理が背景にあると考えられています。
- 不安や混乱:見当識障害(時間や場所が分からなくなること)により、今いる場所が安全だと感じられず、安心できる場所を探そうとする。
- 記憶障害:家にいるのに「家に帰らなければ」と思い込んだり、過去の習慣(出勤、買い物など)を実行しようとしたりする。
- 疎外感や役割の喪失:自分の居場所がないと感じ、かつて活躍していた場所や役割を探しに行こうとすることもあります。
これらの行動は、ご本人からの助けを求めるサイン(SOS)であると理解することが重要です。
「徘徊」の言い換えとして使える具体的な言葉を教えてください
状況に応じて様々な表現が使えます。以下に代表的な例を挙げます。
- 全般的な外出行動に:「ひとり歩き」「お出かけ」「お散歩」
- 目的が分からず動いている様子に:「落ち着かないご様子」「何かお探しですか?」「お部屋を移動されています」
- 介護記録などで客観的に記す場合:「離棟」「離室」
ご本人の様子や状況をよく観察し、最も適切な表現を選ぶことが大切です。
街で困っている様子の高齢者を見かけたらどうすれば良いですか?
まずは、驚かせないように優しく声をかけることが第一歩です。「こんにちは、何かお困りですか?」など、相手を気遣う言葉が良いでしょう。
話を聞く中で、お名前や帰り先が分からないようであれば、無理に聞き出そうとせず、最寄りの交番や警察(110番)、または地域包括支援センターに連絡してください。その方の安全を確保し、専門家へつなぐことが地域住民としてできる大切な支援です。