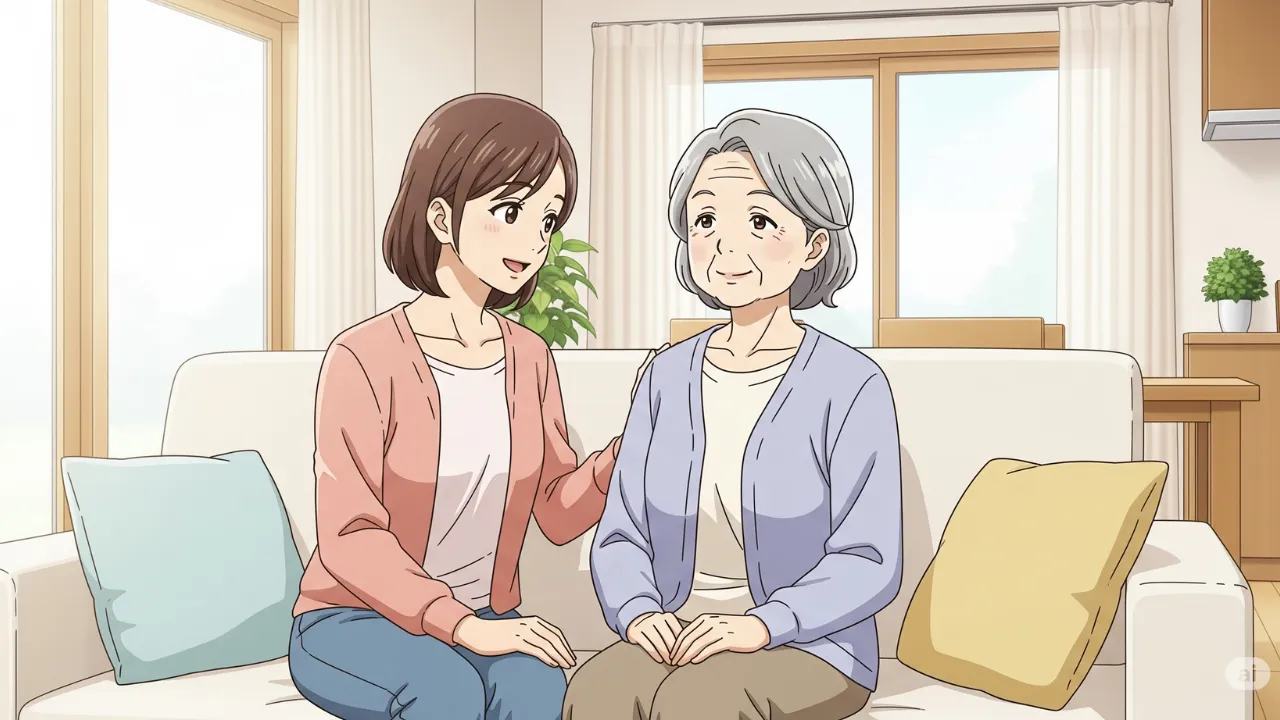はじめに:親を施設に入れた後悔で、自分を責めていませんか?
親御さんを介護施設に入居させた後、「本当にこの選択で良かったのだろうか」「もっと他に方法はなかったのではないか」と、後悔や罪悪感に苛まれていませんか。
在宅での介護に限界を感じ、悩み抜いた末の決断だったはずなのに、ふとした瞬間に自分を責めてしまう。その苦しい気持ちは、決してあなた一人が抱えているものではありません。
親を大切に思うからこそ生まれる、その複雑な感情は、多くのご家族が経験する道です。この記事では、なぜ後悔の念が生まれるのか、その理由を紐解きながら、あなたの心の負担を軽くするための具体的なヒントをお伝えします。
この記事を読み終える頃には、あなたの決断が間違いではなかったと確信し、前向きな気持ちで親御さんと向き合うための一歩を踏み出せるはずです。
なぜ?親を施設に入れたあとに後悔や罪悪感が生まれる5つの理由
親御さんを施設に入れた後に感じる後悔や罪悪感は、親を深く思う気持ちの裏返しでもあります。多くの人が同じような感情の葛藤を経験しています。
まずは、なぜそのような気持ちになるのか、ご自身の状況と照らし合わせながら、心を整理していきましょう。原因を理解するだけでも、気持ちが少し楽になるかもしれません。
理由1:親が「寂しい」「家に帰りたい」と訴えるから
面会に行ったとき、親御さんから力なく「寂しい」「家に帰りたい」と言われると、胸が締め付けられる思いがしますよね。
特に、入居して間もない頃は、環境の変化に対する不安やストレスから「帰宅願望」が強く出ることがあります。認知症の症状がある場合は、その傾向がさらに顕著になることも考えられます。
本人の言葉一つひとつに心が揺れ、「可哀想なことをしてしまった」と自分を責めてしまうのは、自然な反応です。
しかし、それが必ずしも施設での生活が不幸であることを意味するとは限りません。環境の変化への戸惑いは時間とともに和らぐことも多いのです。
理由2:在宅介護という選択肢を諦めてしまったという思い
「もう少し自分が頑張れば、在宅介護を続けられたのではないか」「他の介護サービスを探すなど、やれることがもっとあったはず…」と、過去の選択を悔やむ気持ちも大きな原因です。
在宅介護の限界は、ご家庭の状況や介護者の健康状態によって様々です。
「共倒れ」になってしまう前に専門家の力を借りるという判断は、決して諦めではありません。ご自身と親御さんの双方にとって、より良い生活を守るための勇気ある選択だったという視点も大切です。
長期的に見れば、最も賢明な判断だったと言えるでしょう。
理由3:「自分が楽になった」ことへの後ろめたさ
24時間体制の介護から解放され、自分の時間を取り戻したり、夜間に安心して眠れるようになったり。
その「楽になった」という事実に、まるで親の犠牲の上に自分の平穏が成り立っているかのような、後ろめたい気持ちを感じてしまうことがあります。
しかし、介護者が自身の心と身体の健康を保つことは、介護を続ける上で最も重要なことです。
あなたが心に余裕を取り戻すことで、親御さんに対してより穏やかな気持ちで接することができるようになるのです。自分を労わることも、愛情の表れです。
理由4:世間体や「親不孝」という固定観念に縛られている
「親の面倒は子どもが見るのが当たり前」といった周囲からの無言の圧力や、ご自身の中に根強く残る固定観念が、「親を施設に入れる=親不孝」という罪悪感に繋がることがあります。
しかし、介護の形は時代とともに変化しており、家族だけで抱え込むのではなく、介護保険などの社会制度や専門家の力を借りて支えていくのが現代の主流な考え方です。
あなたの決断は、決して責任を放棄したわけではありません。むしろ、親御さんの安全と幸せを真剣に考えた結果なのです。
社会全体で高齢者を支えるシステムを利用することは、現代における新しい孝行の形と言えるでしょう。
理由5:施設の環境が親に合っていないと感じる不安
見学の時には気づかなかった施設の雰囲気や、スタッフの些細な対応、他の入居者の方の様子を見て、「この場所は本当に親に合っているのだろうか」と不安になることも後悔の一因です。
親御さんの表情が曇っているように見えたり、部屋に閉じこもりがちになったりすると、心配は募る一方でしょう。
施設とのコミュニケーションを密にし、親御さんの状況を共有していくことで、環境に馴染めるようフォローできることもあります。
最初の不適応は時間の経過とともに改善されることも多いため、少し様子を見ることも大切です。
その決断は間違いじゃない。施設入居がもたらす3つのメリット
後悔の念に囚われていると、どうしてもネガティブな側面ばかりに目が行きがちです。
しかし、あなたが下した「施設入居」という決断には、在宅介護では得られなかった大きなメリットもあります。一度立ち止まって、客観的にその価値を見つめ直してみましょう。冷静に振り返ることで、決断の正しさが見えてくるはずです。
メリット1:24時間体制の専門的な介護・医療ケアによる安心
施設には、介護の専門知識と技術を持ったスタッフが24時間常駐しています。夜間の見守りや、急な体調の変化にも迅速に対応してもらえる環境は、ご自宅での介護では得難い最大のメリットです。
特に持病がある方や医療的なケアが必要な方にとっては、看護師が常駐し、協力医療機関と連携している施設の存在は、何物にも代えがたい安心材料となります。
これにより、ご本人の健康と安全が守られ、万が一の事態にも即座に対応できる体制が整っています。家族では判断が難しい医療的な症状も、専門家の目でしっかりと見守られているのです。
この安心感は、在宅介護では決して得られないものでしょう。
メリット2:介護する側の心と身体の負担軽減(介護離職や共倒れの防止)
終わりが見えない介護は、介護者の心と身体を少しずつ蝕んでいきます。介護を理由に仕事を辞める「介護離職」や、介護者まで倒れてしまう「共倒れ」は、決して他人事ではありません。
施設に介護を任せることで、あなた自身の生活や健康、そして仕事を守ることができます。
これは、結果的に長期的な視点で親御さんを支え続けるための基盤を守ることに繋がるのです。介護疲れで倒れてしまっては、誰も幸せになれません。
持続可能な介護の形を選択したことは、賢明な判断だったのです。
メリット3:穏やかな気持ちで親と向き合える時間が生まれる
在宅介護中は、日々の介助に追われ、精神的な余裕を失いがちです。
「介護する側」と「される側」という関係が固定化し、親に対して苛立ってしまう瞬間もあったかもしれません。施設入居によって介護の負担から解放されると、心に余裕が生まれます。
面会に行ったとき、純粋に「家族」として、穏やかな気持ちで親子の時間を過ごせるようになります。
これが、新たな良い関係を築くきっかけになることも少なくありません。介護の重圧から解放されることで、本来の親子の絆を取り戻すことができるのです。
親を施設に入れた後悔を軽くする6つの具体的アクション
親御さんの入居は、家族の関わりの終わりを意味するものではありません。むしろ、ここからが新しい関係の始まりです。
罪悪感や後悔で立ち止まるのではなく、今のあなただからこそできることがあります。具体的な行動を起こすことで、気持ちは前向きに変わっていきます。一歩ずつ、新しい親子関係を築いていきましょう。
アクション1:面会の「量より質」を意識して会いに行く
頻繁に面会に行けないことを気にする必要はありません。大切なのは時間の長さよりも、その質です。
短い時間でも、笑顔で話を聞き、手を握ってあげるだけで、親御さんは安心します。義務感で訪れるのではなく、「顔を見に来たよ」という気持ちで、楽しい雰囲気を作ることを心がけましょう。
思い出話をする、好きな食べ物を差し入れするなど、面会が楽しみな時間になるような工夫も効果的です。
親御さんにとって、あなたの笑顔と温かい言葉こそが何よりの薬になるのです。質の高い時間を過ごすことで、お互いの心が満たされるでしょう。
アクション2:施設のスタッフと積極的にコミュニケーションを取る
施設のスタッフは、一番近くで親御さんの日々の様子を見ている、最も頼りになるパートナーです。面会の際には、担当の介護職員や看護師に声をかけ、「最近の様子はどうですか?」「食事は食べられていますか?」など、積極的に質問しましょう。
自宅での過ごし方や好きなことなどを伝えておくと、スタッフもケアのヒントを得やすくなります。また、地域包括支援センターへの相談も有効です。
信頼関係を築くことが、親御さんの安心な生活に直結します。些細な変化でも気になることがあれば遠慮なく相談し、スタッフと一緒に親御さんを支える姿勢を示すことが大切です。
チーム一丸となってケアにあたることで、より良い環境が整うでしょう。
アクション3:親の部屋を自宅に近い環境に整える
慣れない施設の部屋でも、少しでも自宅の雰囲気に近づけることで、親御さんの心の拠り所になります。
使い慣れた湯飲みやクッション、家族の写真、お気に入りの絵や置物などを飾ってあげましょう。ご本人が大切にしているものを身の回りに置くことで、孤独感や不安が和らぎ、自分の居場所だと感じやすくなります。
季節ごとに飾り付けを変えるのも、良い気分転換になります。春には桜の写真、秋には紅葉の絵など、季節感を取り入れることで、親御さんの心も明るくなるでしょう。
こうした細やかな配慮が、施設での生活を豊かにする大切な要素となります。
アクション4:可能であれば一時帰宅や外出を計画する
体調や施設のルールが許すのであれば、一時帰宅や近所への外出を計画するのも良い方法です。
自宅でゆっくり過ごしたり、馴染みの店で食事をしたりすることで、大きなリフレッシュになります。たとえ施設の敷地内を少し散歩するだけでも、外の空気に触れることは心身に良い刺激を与えます。
ただし、無理は禁物です。ケアマネジャーや施設スタッフとよく相談した上で計画しましょう。
親御さんの体調や精神状態を最優先に考えながら、無理のない範囲で楽しい時間を作ることが大切です。
アクション5:一人で抱え込まずケアマネジャーなどの専門家に相談する
後悔や罪悪感、施設への不満など、モヤモヤした気持ちは一人で抱え込まないでください。
まずは、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。彼らは介護の専門家であると同時に、多くの家族の悩みを聞いてきたプロフェッショナルです。客観的な視点から的確なアドバイスをくれたり、施設との橋渡しをしてくれたりすることもあります。
気持ちを吐き出すだけでも、心が軽くなるはずです。専門家と話すことで、新たな視点や解決策が見つかることも多いものです。たとえば、介護うつチェックリストで自身の状態を確認することもできます。
一人で悩む時間を減らし、前向きな行動につなげていきましょう。
アクション6:自分のための時間を作り、心と体を休ませる
最後に、最も大切なのはあなた自身を労わることです。親御さんのことを心配するあまり、自分のことを後回しにしていませんか?
介護の主役が親御さんから施設に代わった今こそ、意識的に自分のための時間を作り、心と体を休ませてください。趣味を楽しんだり、友人と会ったり、何もしない時間を作ったりと、心身のリフレッシュを心がけましょう。
あなたが元気で笑顔でいることが、結果的に親御さんを安心させる一番の薬になるのです。罪悪感を感じる必要はありません。
自分自身を大切にすることも、親孝行の一つなのです。心の余裕を取り戻すことで、より良い親子関係を築けるでしょう。
それでも後悔の念が消えない…施設から自宅に戻す選択肢
様々な工夫をしても、どうしても「やはり自宅で看たい」という後悔が消えない場合もあるでしょう。その場合、「在宅介護に戻す」という選択肢もゼロではありません。
しかし、感情的な勢いだけで決めるのは危険です。メリットとデメリットを冷静に比較し、現実的な問題をクリアできるか慎重に検討する必要があります。
施設から在宅介護に戻る際のメリット・デメリット
在宅介護に戻ることには、以下のようなメリットとデメリットが考えられます。
- メリット
- 本人の「家に帰りたい」という希望を叶えられる
- 家族が常にそばにいる安心感がある
- 自分たちのペースで介護ができる
- デメリット
- 再び家族の身体的・精神的負担が増大する
- 24時間体制の緊急時対応が難しくなる
- 一度退去すると、同じ施設への再入居が困難になる場合がある
- 在宅介護のための費用(住宅改修、介護サービス費など)が改めて必要になる
安易な決断は、再び共倒れの状態を招く危険性があることを理解しておく必要があります。
自宅に戻す前に確認すべきことと手続きの流れ
もし在宅介護への復帰を真剣に考えるなら、以下の点を必ず確認・準備しましょう。
- ケアマネジャーへの相談:まず最初に、担当のケアマネジャーに意向を伝え、実現可能か、どのような課題があるかを相談します。
- 在宅介護サービスの再検討:訪問介護やデイサービスなど、必要な介護サービスを再度ケアプランに組み込んでもらいます。
- 経済的な見通し:在宅介護に戻った場合の費用をシミュレーションし、経済的に無理がないかを確認します。
- 家族の協力体制の構築:一人に負担が集中しないよう、他の家族や親族との協力体制を改めて話し合います。
- 住宅環境の整備:手すりの設置や段差の解消など、本人が安全に暮らせるよう自宅の環境を見直します。
これらの準備を入念に行った上で、施設側と退去に向けた具体的な手続きを進めていくことになります。親御さんが自宅に戻りたがらない場合は、親を説得する方法も参考にしてみてください。
まとめ:「親を施設に入れた後悔」を乗り越え、新たな親子関係を築くために

親御さんを施設に入れた後に抱く後悔や罪悪感は、あなたが親御さんを深く愛し、大切に思っているからこそ生まれる、ごく自然な感情です。決して自分を責め続ける必要はありません。
施設への入居は、親子の関係の終わりではなく、介護の負担から解放され、より穏やかな気持ちで向き合える新しい関係の始まりだと捉え直してみませんか。
面会の質を高めたり、スタッフと連携したりと、あなたにできることはたくさんあります。一つひとつの行動が、親御さんの安心につながり、あなた自身の後悔の念を和らげてくれるはずです。
一人で抱え込まず、専門家や周りの人の力も借りながら、あなたと親御さんにとって最善の形を見つけていってください。
親を施設に入れた後の後悔に関するよくある質問
親を施設に入れるのは親不孝なのでしょうか?
決して親不孝ではありません。かつては「親の面倒は家で子どもが見るもの」という考え方が一般的でしたが、今は介護の形も多様化しています。
在宅介護の限界を超え、共倒れになる前に、専門家の力を借りて安全な環境を整えることは、親の生活と安全を守るための愛情ある責任ある選択です。
介護の負担を減らし、穏やかな気持ちで面会できる関係を築くほうが、親子双方にとって幸せな場合も多いのです。
親を施設に入れるタイミングや目安はありますか?
明確な基準はありませんが、一般的に以下のような状況が目安とされています。
- 介護者の心身の限界:介護者が不眠や体調不良を抱え、精神的に追い詰められている。
- 安全の確保:認知症による徘徊や火の不始末など、在宅での生活に危険が伴うようになった。
- 専門的なケアの必要性:嚥下(えんげ)困難や、床ずれ、医療的なケアなど、家庭での対応が難しくなった。
このようなサインが見られたら、ケアマネジャーに相談し、施設入居を具体的な選択肢として検討するタイミングと言えるでしょう。
嫌がる親や頑固な親を施設に入れるにはどうすればいいですか?
本人が嫌がっている場合、無理やり入居を進めるのは困難ですし、後々のトラブルの原因にもなります。まずは本人の気持ちを十分に聞き、「なぜ施設が嫌なのか」という理由を探ることが大切です。
その上で、「体験入居」や「ショートステイ」を利用して、施設の雰囲気だけでも感じてもらうのも一つの方法です。また、家族が話すよりも、ケアマネジャーや医師など、第三者の専門家から施設の必要性を説明してもらうと、聞き入れてくれるケースもあります。
施設に入居すると費用はいくらくらいかかりますか?
費用は、入居する施設の種類によって大きく異なります。費用が比較的安い「特別養護老人ホーム(特養)」のような公的施設は、月額利用料が10万円前後からですが、入居待機者が多い傾向にあります。
一方、「有料老人ホーム」などの民間施設は、入居一時金が0円から数千万円、月額利用料も15万円~30万円以上と様々です。必要な費用は要介護度や所得によっても変わるため、ケアマネジャーに相談したり、候補となる施設に直接問い合わせて詳細な見積もりを取ったりすることが重要です。
良い施設とそうでない施設の見分け方を教えてください。
いくつかポイントがありますが、必ず複数の施設を見学して比較検討することが大切です。チェックすべきポイントは以下の通りです。
- スタッフと入居者の表情:スタッフが笑顔で働いているか、入居者の表情が穏やかか。
- 施設の清潔感と匂い:共用スペースや居室が清潔に保たれているか、不快な匂いがしないか。
- スタッフの対応:見学者への挨拶や説明が丁寧か、質問に誠実に答えてくれるか。
- 情報公開:料金体系や運営方針に関する情報をきちんと公開しているか。
これらの点を総合的に見て、家族として「ここなら安心して任せられる」と感じられる場所を選ぶことが大切です。
施設に入ると認知症は悪化してしまうのでしょうか?
環境が大きく変わることで、一時的に混乱して症状が進行したように見える(せん妄など)ことはあります。しかし、必ずしも悪化するわけではありません。
むしろ、規則正しい生活リズムや栄養バランスの取れた食事、専門スタッフによる適切なケア、レクリエーションなどを通じて他者との交流が増えることで、症状が穏やかになったり、進行が緩やかになったりするケースも少なくありません。
大切なのは、施設と連携し、本人の状態に合わせたケアをしてもらうことです。
親が施設に入ったら、家族は何をすればいいですか?
施設に任せきりにするのではなく、家族としての関わりを続けることが大切です。具体的には、定期的な面会が最も重要です。
短い時間でも顔を見せることで、親御さんは安心し、孤立感を防ぐことができます。また、施設のスタッフと積極的にコミュニケーションを取り、親御さんの様子を共有し合うことも大切です。
衣類の入れ替えや、季節に合わせた差し入れなど、細やかな気配りも喜ばれるでしょう。介護の主役ではなくなっても、家族としての役割は続きます。