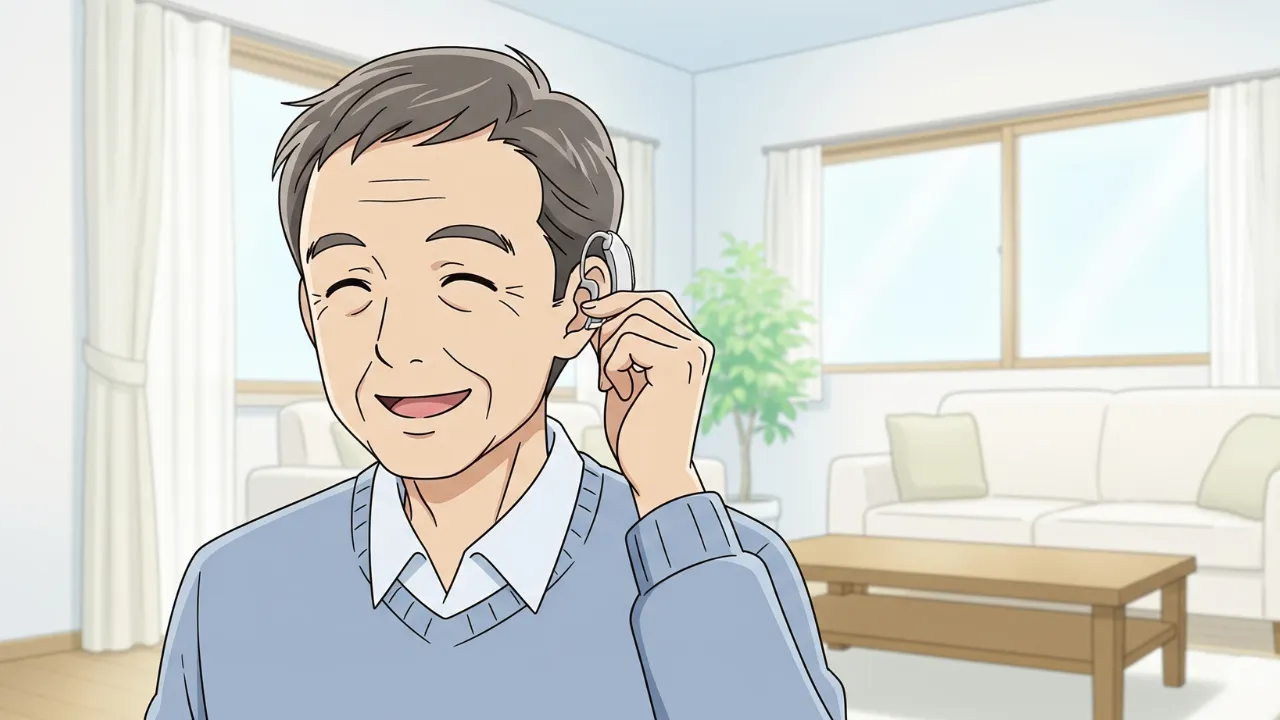はじめに:大切なご家族のために。後悔しない補聴器選びを始めましょう
「最近、親との会話が噛み合わない」「テレビの音量が大きい」と感じることはありませんか。聴力の低下は自然な変化ですが、ご本人やご家族にとってコミュニケーションの壁となり、ストレスや孤独感につながることがあります。そんなとき、大きな助けとなるのが「補聴器」です。
しかし、いざ補聴器を選ぼうとすると「種類が多すぎて何が違うの?」「価格も様々で、どれが適切かわからない」といった新たな悩みが出てくるものです。高価な買い物だからこそ、絶対に失敗したくないと考えるのは当然のことです。
この記事では、高齢者向け補聴器の基本的な知識から、口コミで評判の機種を集めたおすすめランキング、購入で失敗しないための具体的な手順まで、専門的な内容を分かりやすく解説します。ご家族にぴったりの一台を見つけるための確かな知識が身につき、再び会話のあふれる楽しい毎日を取り戻すための一歩を踏み出せます。
補聴器と集音器は別物!まず知っておきたい基本的な違い
補聴器の検討を始めると、よく似た機器として「集音器」という言葉を目にすることがあります。価格が比較的安いため魅力的に感じるかもしれませんが、この二つは全く異なるものです。大切な耳の健康を守るために、まずはその決定的な違いを理解しておきましょう。
補聴器が個々の聴力に合わせて音を調整する医療機器であるのに対し、集音器は音を全体的に大きくする家電製品です。この違いが、聞こえの質や安全性に大きく影響します。正しい知識を持つことが、適切な製品選びの第一歩です。
医療機器としての補聴器、音を大きくする集音器
補聴器と集音器の最大の違いは、補聴器が厚生労働省に認められた「管理医療機器」であるのに対し、集音器は家電製品という点です。補聴器は使用者の聴力に合わせ、専門家が「言葉の聞き取り」に必要な音域を精密に調整して増幅します。
一方、集音器は基本的に周囲の音を区別なく大きくするものです。そのため、必要な会話だけでなく雑音まで大きくなり、かえって聞き取りにくくなる場合があります。ただし、近年は調整機能を備えた集音器も登場していますが、その役割は補聴器とは異なります。
専門家による調整が不可欠な理由
人の聴力は、指紋のように一人ひとり異なります。どの高さの音が、どのくらい聞こえにくいのかは人それぞれです。そのため補聴器は、購入時に「認定補聴器技能者」などの専門家による精密な調整(フィッティング)が不可欠です。
この調整を行わずに音を大きくするだけの機器を使うと、快適な聞こえが得られないばかりか、かえって耳に負担をかける危険性もあります。安全かつ効果的に聴力をサポートするためには、専門家のもとでご自身の聞こえに合わせた補聴器を選ぶことが極めて重要です。
【図解】高齢者向け補聴器の選び方5つのステップ
ここからは、実際に補聴器を選ぶ際の具体的な5つのステップを解説します。形状、聴力レベル、機能、価格、そして片耳か両耳か。これらのポイントを押さえることで、数ある選択肢の中から最適な一台を絞り込むことができます。
どのステップも、ご自身やご家族のライフスタイル、そして聞こえの状態を考慮する上で非常に重要です。一つずつ確認しながら、後悔しない補聴器選びを進めていきましょう。
ステップ1:形状で選ぶ|使いやすさと見た目のバランス
補聴器には、大きく分けて「耳かけ型」「耳あな型」「ポケット型」の3つの形状があります。それぞれに長所と短所があるため、使う方のライフスタイルや何を重視するかによって選ぶことが大切です。
例えば、操作のしやすさを優先するのか、それとも目立たないことを重視するのかで選択は変わります。ご本人の希望を丁寧にヒアリングし、最も快適に使える形状を見つけましょう。
耳かけ型:操作しやすく種類が豊富で様々な聴力に対応
耳の後ろに本体をかけて使用する、最も標準的なタイプです。比較的操作がしやすく、軽度から重度の難聴まで幅広い聴力レベルに対応できるのが魅力です。カラーバリエーションやデザインも豊富です。ただし、マスクやメガネを使用する方は、耳周りが窮屈に感じることがあります。
耳あな型:目立たないがオーダーメイドなど価格は高め
耳のあなにすっぽりと収まるタイプで、外からはほとんど見えないほど小型なため、補聴器を着けていることを知られたくない方に人気です。風切り音がしにくいという利点もあります。一方で、小型なため操作に慣れが必要なことや、オーダーメイド製作になることが多く価格が高くなる傾向があります。
ポケット型:操作が簡単でパワフルだがコードが邪魔になることも
本体をポケットやカバンに入れ、コードで繋がったイヤホンを耳に入れて使います。本体が大きく、ボタンやダイヤルでの音量調整などが非常に分かりやすく、操作が簡単なのが最大の特徴です。パワーも強く、高度・重度難聴の方にも対応できます。しかし、常にコードがあるため、煩わしさを感じる方もいます。
ステップ2:聴力レベルで選ぶ|軽度・中等度・高度・重度
補聴器は、使用者の聴力レベルに合わせて適切なものを選ぶ必要があります。難聴の程度は「軽度」「中等度」「高度」「重度」に分類され、それぞれ対応する補聴器のパワーが異なります。自己判断で選ぶのは絶対に避けるべきです。
パワーが弱すぎて効果がなかったり、逆に強すぎて不快に感じたりする原因になります。まずは必ず耳鼻咽喉科を受診し、医師の診断のもとでご自身の正確な聴力レベルを把握することから始めましょう。
ステップ3:機能で選ぶ|生活がもっと快適になる便利機能
近年のデジタル補聴器は、単に音を大きくするだけでなく、生活を豊かにするための様々な便利機能が搭載されています。どのような機能があれば、より快適な毎日を送れるかを想像しながら、必要な機能を見極めましょう。
例えば、電池交換の手間をなくしたい、騒がしい場所でも会話を楽しみたい、テレビの音を直接聞きたいなど、具体的な要望に合わせて機能を選ぶことが満足度を高める鍵です。
充電式:電池交換の手間がなく高齢者にも使いやすい
従来の電池交換式に代わり、現在主流となっているのが充電式の補聴器です。専用の充電器に置くだけで手軽に充電できるため、小さな電池を交換する手間がなく、高齢者の方でも非常に使いやすいと人気です。就寝中に充電しておけば、日中の電池切れの心配もありません。
雑音抑制・ハウリング抑制:クリアな聞こえを実現
「騒がしい場所だと会話が聞き取れない」という悩みを解決するのが雑音抑制機能です。周囲の不要なノイズを自動で抑え、聞きたい会話の音声を際立たせてくれます。また、補聴器から「ピーピー」という音が漏れるハウリングを抑制する機能も、快適な使用には欠かせません。
ワイヤレス(Bluetooth)機能:テレビやスマホと連携して楽しむ
Bluetoothを搭載した機種では、テレビやスマートフォン、音楽プレーヤーの音声を直接補聴器で聞くことができます。家族に気兼ねなくテレビを好きな音量で楽しんだり、電話の声をクリアに聞いたりできるため、生活の質を大きく向上させてくれる便利な機能です。
ステップ4:価格と性能のバランスで選ぶ|値段による違いは?
補聴器の価格は、片耳で5万円程度から60万円程度までと非常に幅広いです。この価格差は、主に内蔵されているコンピューターチップの性能や、搭載されている機能によって生まれます。
高価なモデルほど、騒音下での会話を助ける機能や自動音質調整機能が優れています。しかし、必ずしも高価なものが最適とは限りません。ご自身の生活スタイルと予算に合わせて、専門家と相談しながら選ぶことが重要です。
ステップ5:両耳装用か片耳装用かを選ぶ|自然な聞こえと方向感覚
聴力が両耳とも低下している場合、原則として補聴器は両耳に着けることが推奨されます。両耳に着けることで、左右の耳から入る音のバランスが取れ、音の方向感覚が掴みやすくなるからです。
また、騒音の中でも言葉を聞き取る能力が向上したり、片耳だけで聞くよりも疲れにくかったりといった多くの利点があります。もちろん、聴力の状態や予算に応じて片耳での使用も選択肢となりますので、専門家とよく相談しましょう。
高齢者向け補聴器おすすめランキング|口コミ・評判で人気!
ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、実際の利用者からの口コミや評判が良い、高齢者におすすめの補聴器をランキング形式でご紹介します。どの製品も信頼できるメーカーの人気モデルですが、あくまで一般的な評価です。
最終的には、ご自身の耳で試聴し、聞こえ方や着け心地の相性を確かめることが最も重要です。このランキングを参考に、気になるモデルを見つけて試聴の候補にしてみてください。
1位|エーストーンフィット2
「エーストーンフィット2」は、耳穴に収まる超小型の高性能デジタル補聴器です。外からほとんど見えず、着けていることを忘れるほど軽いため、初めての方でも安心して使えます。12チャンネルの高度な処理で、クリアで自然な聞こえを実現します。
耳栓不要で、自然な聞こえ心地
高度なデジタル技術で不快なピーピー音(ハウリング)を抑制します。耳栓なしで装着でき、自分の声がこもらず自然な感覚で会話を楽しめるのが特徴です。閉塞感が苦手な方にも最適で、ストレスのない聞こえ心地を提供します。
12チャンネルで雑音の中でも会話が明瞭
音を12の周波数帯に分けて処理するため、街中の騒音を抑え、聞きたい会話をくっきりと浮かび上がらせます。レストランなど、さまざまな場面で相手の話が聞き取りやすくなり、会話に自信が持てるようになります。
スマホで簡単、音量調整
無料の専用スマートフォンアプリがリモコン代わりになり、手元のスマホで簡単に音量調整が可能です。本体が小さくても、使い慣れたスマホで直感的に操作できるので、いつでも快適な聞こえを維持できます。
こんな人におすすめ
- 初めて補聴器を使う方
- 補聴器が目立つのが嫌な方
- 騒がしい場所での会話が多い方
「聞こえ」が変わると毎日がもっと楽しくなります。諦めていた会話の輪にもう一度参加しませんか。本製品は軽度から中等度の難聴に対応しますが、正確な対応範囲はメーカー公式情報で確認しましょう。
2位|オンキョー 耳あな型補聴器 OHS-D31
オーディオの老舗オンキョーが開発した耳あな型補聴器です。長年の音響技術を活かし、自然でクリアな聞こえを追求しました。小型で目立ちにくく、快適な着け心地であなたの毎日をサポートします。
オンキョーならではの澄んだ音質
オーディオメーカーとしての経験と技術を結集し、聞き疲れしにくい自然な音質を実現しました。人の声やテレビの音が、余計な雑音なく明瞭にあなたの耳に届き、日常の会話がもっと楽しくなります。
左右の耳に合わせた快適設計
左右それぞれの耳の形に合わせて設計されているため、一日中着けていても快適です。耳の中にすっぽりと収まり、外からはほとんど見えないので、周囲の目を気にすることなく使用できます。
雑音・不快な音をしっかり抑制
不快なピーピー音(ハウリング)や周囲の雑音を自動で抑制する機能を搭載。騒がしい場所でも聞きたい声が際立ち、ストレスなく会話に集中できるため、お出かけがもっと楽しくなります。
こんな人におすすめ
- 音質にこだわりたい方
- 目立たない補聴器が良い方
- 一日中快適に使いたい方
聞こえのストレスから解放され、もっと会話を楽しみませんか。オンキョーの技術が詰まったこの補聴器で、聞こえる喜びをもう一度。自信をもって過ごせる毎日が、ここから始まります。
3位|Vibe Nano8
Vibe史上最小サイズの耳あな型補聴器です。着けていることが分からないほど小さく、聞こえの悩みをスマートに解決します。アプリで自分好みの聞こえに調整できる、次世代の聞こえのサポーターです。
誰にも気づかれない超小型設計
耳の奥に完全に収まるCIC型で、正面からも横からもほとんど見えません。補聴器の見た目に抵抗がある方でも、人の目を気にすることなく、自信を持って毎日を過ごせます。
スマホで簡単「セルフ調整」
専用アプリを使えば、お店に行かなくても自分で聞こえの調整ができます。聴力測定から音質の微調整まで、いつでもあなたに最適な聞こえを手に入れることが可能です。
置くだけ無線充電と優れた耐久性
面倒な電池交換は不要で、充電ケースに置くだけで充電が完了します。汗や雨にも強いIP68の防じん・防水仕様なので、活動的な場面でも安心して使えます。
こんな人におすすめ
- 補聴器の見た目が気になる方
- 自分で音質を調整したい方
- 活動的で汗をかきやすい方
見えない補聴器で、聞こえる自信を取り戻しませんか。最新の技術が詰まったVibe Nano8が、あなたの生活をより豊かで快適なものに変えていきます。
4位|Vibe Go
見た目はまるでワイヤレスイヤホン。補聴器と気づかれずに、聞こえをサポートする新しい形のデバイスです。買ってすぐに使える手軽さで、あなたの聞こえの世界を自然に広げます。
イヤホンにしか見えないデザイン
補聴器特有の見た目を完全に払拭した、スタイリッシュなイヤホン型です。ファッションの一部として、周囲の目を気にすることなく、毎日気軽にお使いいただけます。
音楽もハンズフリー通話もこれ一台で
Bluetooth機能を搭載しており、スマートフォンと連携して音楽鑑賞や通話が可能です。補聴器とイヤホンの1台2役をこなし、あなたの生活をより豊かで便利にします。
アプリの案内に従うだけで準備完了
専門家のもとへ行かなくても、専用アプリの案内に従うだけで、自分に合った聞こえに調整できます。購入したその日から、すぐにクリアな聞こえを体験することが可能です。
こんな人におすすめ
- 補聴器の見た目に抵抗がある方
- 音楽や通話も楽しみたい方
- 手軽に補聴器を始めたい方
聞こえの補助をもっとお洒落で身近なものに。Vibe Goはあなたのライフスタイルに自然に寄り添います。聞こえる楽しさと便利さを、この一台で手に入れてください。
5位|デジミミ3
世界的な補聴器メーカーが作った、手軽な耳あな型補聴器です。難しい調整は一切不要で、買ったその日から使えます。信頼のデジタル性能で、会話の聞こえをしっかりと支える、入門用に最適な一台です。
指先ひとつで、かんたん操作
本体のダイヤルを回すだけで、自分で簡単に音量を変えられます。スマートフォンや面倒な設定が苦手な方でも、迷うことなく直感的に扱えるので安心。いつでも快適な音量に調整できます。
信頼のデジタル性能で会話が明瞭
不快なピーピー音や周りの雑音を抑える、確かなデジタル機能を搭載。聞きたい会話がクリアになるので、お出かけや家族との団らんがもっと楽しくなります。ストレスのない聞こえを実現します。
小さく目立たない耳あな型
耳の中にすっぽりと収まる小型設計で、装着していることが外から分かりにくいのが特徴です。補聴器の見た目が気になる方でも、周りの目を気にせず、いつでも快適な聞こえを得られます。
こんな人におすすめ
- 簡単な操作を求める方
- 買ってすぐに使いたい方
- 手頃で信頼できる製品が良い方
「聞こえ」の悩みを、この一台で手軽に解決しませんか。デジミミ3が、あなたの「聞く」を助け、毎日を明るくします。確かな聞こえで、会話の輪に加わる喜びを再び感じてください。
評判の良い人気メーカーはどこ?主要6大メーカーの特徴を比較
補聴器選びでは、メーカーごとの特徴を知ることも重要です。現在、世界の補聴器市場は「6大メーカー」と呼ばれる企業グループがその大半のシェアを占めています。どのメーカーも優れた技術を持っていますが、音作りの方針や得意な分野が異なります。
それぞれのメーカーが持つ強みを理解することで、より自分の要望に合った補聴器を見つけやすくなります。各社の特徴を簡単にご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
シグニア(ドイツ):スタイリッシュなデザインと最新技術
シーメンスの補聴器部門を前身とするメーカーです。洗練されたスタイリッシュなデザインに定評があり、補聴器に見えないイヤホンのような形状の製品も人気です。ご自身の声が響きにくい独自の音声処理技術も特徴で、初めての方でも違和感なく使いやすいと評判です。
フォナック(スイス):聞こえの多様なニーズに対応する技術力
世界シェアNo.1を誇る補聴器のリーディングカンパニーです。子供から高齢者まで、また軽度から重度難聴まで、あらゆる聞こえの要望に対応する高い技術力が強みです。特に騒音下での言葉の聞き取り性能には定評があり、活動的な生活を送る方から絶大な支持を得ています。
オーティコン(デンマーク):脳から聞こえを考える独自の哲学
「BrainHearing(ブレインヒアリング)」という独自の哲学を掲げ、単に音を耳に届けるだけでなく、脳が音を自然に理解する過程をサポートすることを目指しています。360度周囲の音環境を捉え、脳にやさしい自然な聞こえを提供することに注力しています。
GNリサウンド(デンマーク):スマートフォン連携と自然な音質
世界で初めてスマートフォンと直接連携する補聴器を開発したメーカーとして知られています。iPhoneやAndroidとの接続性に優れ、アプリを使った細かい調整も可能です。ワイヤレス技術の先進性に加え、屋外での風切り音対策など、自然な音質を追求する技術も高く評価されています。
スターキー(アメリカ):オーダーメイドとAI搭載補聴器の先駆者
オーダーメイドの耳あな型補聴器に長い歴史と強みを持つメーカーです。近年では、世界で初めてAIを搭載し、転倒検出や翻訳機能まで備えた多機能な補聴器を開発するなど、業界をリードする革新的な技術開発で注目を集めています。
ワイデックス(デンマーク):自然でひずみの少ないクリアな音質
「WIDEX SOUND(ワイデックスサウンド)」と呼ばれる、ひずみの少ない限りなく自然な音質にこだわりを持つメーカーです。特に音楽を楽しむ方からの評価が高く、ダイナミックレンジの広い、豊かでクリアな音の再現性を追求しています。
補聴器の購入で失敗しないために|相談からアフターケアまでの流れ
補聴器は、購入して終わりではありません。むしろ、購入してからが本当のスタートです。ご自身の聴力にぴったり合うように調整を重ねていく必要があります。ここでは、購入で後悔しないための正しい手順と注意点について解説します。
専門家への相談から、試聴、購入後のメンテナンスまで、一連の流れを理解しておくことが大切です。正しい手順を踏むことで、補聴器の効果を最大限に引き出すことができます。
どこで買うのが良い?まずは耳鼻科医へ相談を
「聞こえにくい」と感じたら、自己判断で販売店に行く前に、まずは耳鼻咽喉科を受診してください。難聴には、加齢によるもの以外に、病気が原因の場合もあります。
治療によって聴力が回復するケースもあるため、最初に医師の診察を受け、難聴の原因を正確に把握することが非常に重要です。その上で補聴器が必要と判断されたら、次のステップに進みましょう。
認定補聴器技能者がいる専門店でのフィッティングが重要
補聴器の購入は、専門的な知識と技術を持つ「認定補聴器技能者」が在籍する専門店をおすすめします。認定補聴器技能者は、聴力測定の結果や使用環境、ご本人の要望を詳しくヒアリングし、最適な機種を選定してくれます。
そして、最も重要な「フィッティング(調整)」を時間をかけて丁寧に行い、あなただけの聞こえを作り上げてくれます。この調整の質が、補聴器の満足度を大きく左右します。
購入前に試せる!補聴器の無料レンタルサービスを活用しよう
多くの補聴器販売店では、購入前に実際の補聴器を日常生活で試せるレンタルサービスを実施しています。普段の生活環境で試すことで、その補聴器が本当に自分に合っているかを確認できます。
自宅でのテレビの音や家族との会話、外出先の騒音の中など、様々な場面で使い心地を確かめましょう。高価な買い物ですので、この制度を積極的に活用し、納得した上で購入に進むことが大切です。
【要チェック】補聴器購入で使える補助金・助成金制度
補聴器の購入には、公的な補助制度を利用できる場合があります。代表的なものは、身体障害者手帳(聴覚障害)を持つ方が対象の「障害者総合支援法」に基づく補装具費支給制度です。この制度を利用すると、原則として購入費用の大半が支給されます。
また、お住まいの市区町村によっては独自の助成金制度を設けている場合があります。これらの制度を利用するには、耳鼻咽喉科医の診断書や所定の手続きが必要です。まずはかかりつけ医やお住まいの自治体の福祉課に問い合わせてみましょう。
「年寄りくさい」は昔の話。高齢者が補聴器を嫌がる理由と家族ができること
ご家族のために良かれと思って補聴器を勧めても、当のご本人が「着けたくない」と拒否してしまうことは少なくありません。その背景には、ご本人なりの複雑な心理があります。無理強いはせず、まずはその気持ちに寄り添うことが大切です。
なぜ着けたくないのか、その理由を理解しようと努めることが、解決への第一歩です。ご家族の温かいサポートが、ご本人の心を動かすきっかけになります。
なぜ嫌がる?考えられる心理的な理由と対処法
高齢の方が補聴器に抵抗を感じる理由は様々です。見た目の問題や、老化を認めたくないという気持ちが関係していることが多いようです。まずは、なぜ嫌がるのか、その気持ちを理解しようと努めましょう。
- 老化を認めたくない:補聴器が「老い」の象徴のように感じられ、受け入れたくないというプライドが関係している場合があります。
- 見た目が気になる:「年寄りくさい」「格好悪い」というイメージがあり、人目が気になるという理由です。
- 過去の悪いイメージ:昔の補聴器の「ピーピーうるさい」「雑音ばかり聞こえる」といった悪い印象を持っている場合があります。
これらの気持ちに対し、頭ごなしに否定するのではなく、「そうだよね、気になるよね」と一度受け止めることが重要です。その上で、最近の補聴器はデザインも性能も大きく進化していることを伝えましょう。
無理強いは逆効果!家族が寄り添いサポートできること
本人の気持ちを無視して無理強いをすると、かえって頑なになってしまいます。ご家族ができることは、焦らず、本人のペースに合わせてサポートすることです。具体的な声かけの例をいくつかご紹介します。
- 聞こえない不便さに共感する:「聞き返すのも大変だよね」「会話が聞こえないと寂しいよね」と、本人の不便さに寄り添う言葉をかけましょう。
- ポジティブな未来を話す:「補聴器をつけたら、お孫さんとの会話がもっと楽しくなるよ」「趣味の集まりでも、みんなの話がよく聞こえるよ」など、明るい未来を想像させましょう。
- 一緒に情報収集をする:「最近はこんなにお洒落な補聴器があるんだって」とカタログを見せたり、「話を聞きに行くだけ行ってみない?」と専門店への同行を提案したりしましょう。
大切なのは、補聴器は「本人のため」であり、「家族のため」でもあると伝えることです。ご家族の温かいサポートが、ご本人の前向きな一歩に繋がります。
まとめ:最適な補聴器で、会話のあふれる毎日を取り戻そう
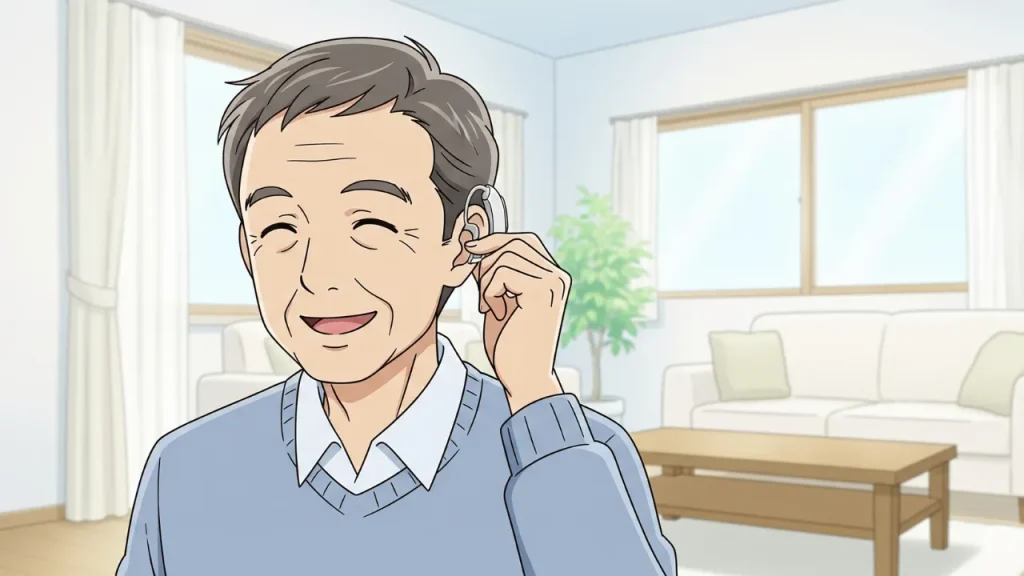
高齢者向けの補聴器選びは、分からないことだらけで不安に感じるかもしれません。しかし、正しいステップを踏めば、ご家族にぴったりの一台は必ず見つかります。最も大切なのは、専門家としっかり相談することです。
この記事で解説した重要なポイントを最後にもう一度おさらいしましょう。
- まずは耳鼻咽喉科を受診し、難聴の原因と聴力レベルを正確に知る。
- 専門家(認定補聴器技能者)がいるお店で相談し、ライフスタイルに合った機種を選ぶ。
- レンタル制度を活用し、実際の生活環境で使い心地を試す。
- 購入後も定期的な調整とメンテナンスを欠かさない。
最適な補聴器は、単に聞こえを補うだけでなく、ご本人の自信や社会との繋がり、そして何よりご家族との温かいコミュニケーションを取り戻してくれる大切なパートナーになります。この記事が、あなたの後悔しない補聴器選びの一助となれば幸いです。
高齢者の補聴器に関するよくある質問
補聴器で評判の良いメーカーは?
A. 特定のメーカーが一番良い、と一概に言うことはできません。本文でご紹介した世界6大メーカー(シグニア、フォナックなど)は、いずれも高い技術力と実績があります。メーカーごとに音質の味付けやデザイン、得意な技術が異なるため、複数のメーカーの製品を実際に試聴し、ご自身が最も「快適」と感じるものを選ぶのがおすすめです。
天皇陛下が愛用している補聴器のメーカーはどこですか?
A. 宮内庁からの公式な発表はありませんが、上皇陛下におかれましては、デンマークの「GNリサウンド」社の補聴器をご愛用されていると言われています。報道などで耳かけ式の補聴器をお着けになっているお姿が拝見されることがあります。ただし、これは公の情報ではないため、あくまで参考程度にお考えください。
日本で一番売れている補聴器はどれですか?
A. 特定の一機種が突出して売れているという公式なデータはありません。人気が高いのは、主要メーカーが販売している「充電式の耳かけ型補聴器」です。電池交換の手間がない利便性や、幅広い聴力に対応できる汎用性から多くの方に選ばれています。ただし、一番売れているものが、あなたにとって一番良い補聴器とは限りません。
高齢者の補聴器の平均的な値段はいくらですか?
A. 補聴器の価格は性能によって大きく異なりますが、片耳で約15万円〜30万円、両耳で約30万円〜60万円程度が一般的な目安です。価格帯としては、片耳5万円程度の基本的なモデルから、60万円を超える高性能なモデルまで幅広く存在します。ご自身の生活環境や必要な機能、予算などを専門家とよく相談して決めることが大切です。
高い補聴器と安い補聴器は何が違うのですか?
A. 主な違いは、内蔵されているコンピューターチップの性能と、搭載機能の多さです。高価格帯の補聴器ほど、雑音を効果的に抑えながら会話を聞き取りやすくする機能や、周囲の環境を自動で認識して音質を最適化する機能が優れています。また、Bluetooth連携などの付加機能も価格に影響します。
補聴器の購入に補助金は出ますか?保険適用になりますか?
A. 補聴器の購入は、公的医療保険(健康保険)の適用対象外です。ただし、聴覚障害で身体障害者手帳をお持ちの場合は、「障害者総合支援法」に基づいて購入費用の一部が支給される制度があります。利用には耳鼻咽喉科医による「意見書」などの書類提出と手続きが必要です。まずはお住まいの市区町村の福祉担当窓口にご相談ください。
補聴器は耳掛け式と耳穴式のどちらが良いですか?
A. どちらが良いかは、使用する方の聴力レベル、手の器用さ、ライフスタイルによって異なります。耳かけ式は操作がしやすく幅広い聴力に対応できるメリットがあり、耳あな式は目立ちにくいという大きなメリットがあります。それぞれの長所と短所を理解した上で、ご自身が最も快適に使えると感じるタイプを選ぶのが一番です。
一番目立たない補聴器はどのタイプですか?
A. 最も目立たないのは、耳のあなの奥深くに収まる「CIC(シーアイシー)」や、さらに小さい「IIC(アイアイシー)」と呼ばれる耳あな型のタイプです。これらは外から見てもほとんど装着していることが分かりません。ただし、非常に小型なため、対応できる聴力の範囲が限られたり、搭載できる機能が制限されたりする場合があります。
補聴器の耳穴型にはどんなデメリットがありますか?
A. 耳あな型の主なデメリットとしては、①自分の声がこもって響くように感じることがある、②耳あなを塞ぐため閉塞感を感じやすい、③小型のため電池交換や操作がしにくい場合がある、④耳垢や湿気の影響を受けやすい、などが挙げられます。最近はこれらのデメリットを軽減する技術も進んでいます。
「集音器はおすすめしない」と言われる理由は何ですか?
A. 集音器は、個人の聴力に合わせて音を調整する機能がない「家電製品」だからです。必要な音も不要な雑音も関係なく一律に増幅するため、かえって言葉が聞き取りにくくなったり、大きすぎる音で耳を痛めてしまったりするリスクがあります。安全かつ効果的に聞こえを補うためには、必ず専門家が調整を行う「医療機器」である補聴器を選んでください。
補聴器はどこで買うのが良いですか?
A. まずは耳鼻咽喉科を受診し、その上で「認定補聴器技能者」が在籍する補聴器専門店で購入することを強く推奨します。デパートや眼鏡店でも取り扱いはありますが、聞こえに関する深い知識と豊富な経験を持つ専門家がいるお店を選ぶことが、購入後の満足度を大きく左右します。
高齢の親が補聴器を嫌がるのですが、どうすれば良いですか?
A. 無理強いは絶対に禁物です。まずは「年寄りくさい」「面倒だ」といったご本人の気持ちを否定せずに受け止め、共感することが第一歩です。その上で、最近の補聴器はとても小さくお洒落なデザインであることを見せたり、「話を聞くだけ」「試してみるだけ」と誘ったりして、少しずつ関心を持ってもらうのが良いでしょう。