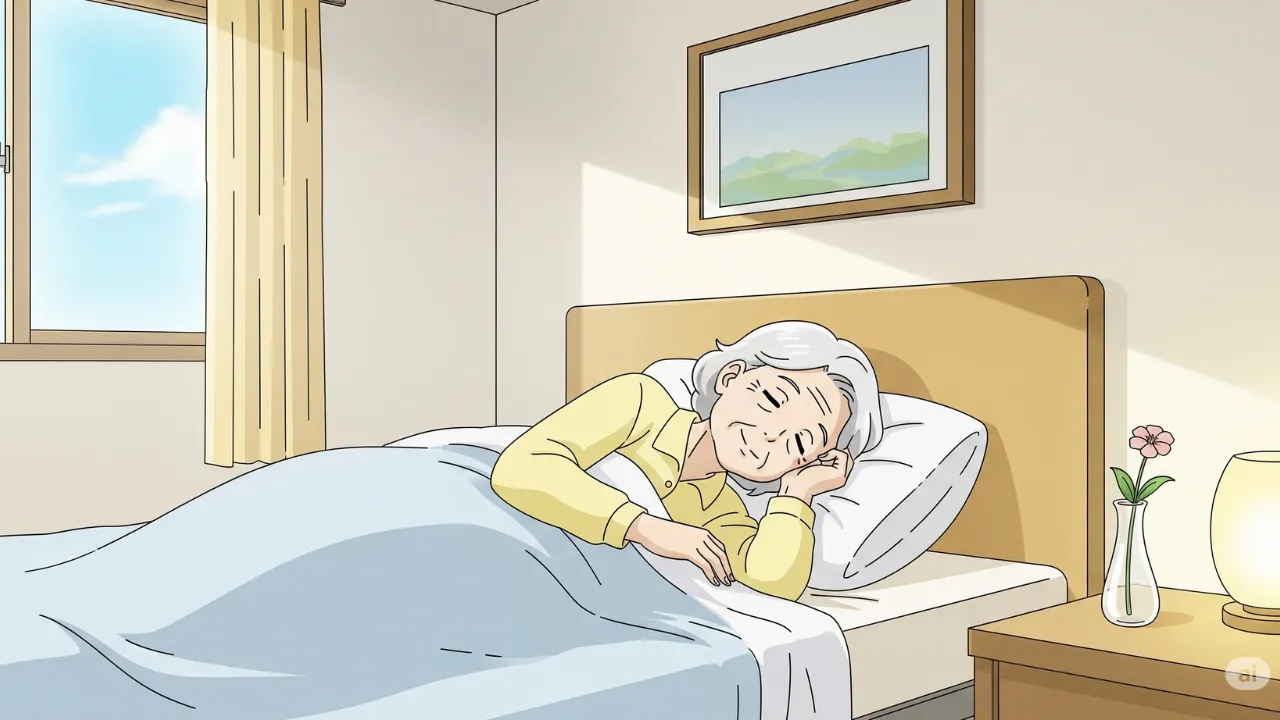はじめに:高齢の親御さん、ご自身の寝起きに不安はありませんか?
「最近、朝布団からスッと起き上がれなくなった」「離れて暮らす親の足腰が弱ってきて、転倒しないか心配だ」と感じていませんか? 年齢を重ねると、このようなお悩みが増えるものです。長年慣れ親しんだ布団での生活は良いものですが、毎日の「起き上がる」「立ち上がる」という動作が、知らず知らずのうちに身体に負担をかけていることがあります。
この記事では、そんなお悩みを解決する「高齢者が使いやすいベッド」について、選び方のポイントからおすすめの製品まで詳しく解説いたします。身体への負担を軽くし、安全で快適な毎日を送るための最適な一台を一緒に見つけていきましょう。
布団からベッドに変えるだけで、生活はもっと安全・快適になります
「ベッド」と聞くと、介護をイメージして「まだ早い」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、現在のベッドはデザイン性が高く、日常生活をより快適にする機能が充実しています。 布団からベッドに変えることで、転倒のリスクを減らし、ご本人様だけでなくご家族の安心にもつながるのです。
この記事が、皆さまのベッド選びの確かな道しるべとなり、これからの生活をより豊かにするきっかけとなれば幸いです。まずは、なぜ高齢者の方にベッドがおすすめなのか、その理由から詳しく見ていきましょう。
そもそも高齢者にベッドは必要?布団との違いを比較
高齢のご本人様やご家族にとって、寝具を布団からベッドへ切り替えることは大きな変化となるでしょう。特に、畳の部屋で布団を敷くスタイルに慣れていると、ベッドのある生活はイメージしにくいかもしれません。 しかし、身体の変化に合わせて寝具を見直すことは、健康で自立した生活を長く続けるために非常に重要です。
ここでは、ベッドを利用する具体的なメリットと、知っておくべきデメリットを比較検討していきます。ご自身やご家族にとって最適な選択をするための参考にしてください。
高齢者がベッドを使う4つのメリット
布団にはない、ベッドならではのメリットは主に4つあります。日々の身体への負担をどれだけ軽減できるか、具体的なポイントを見ていきましょう。 これらのメリットは、生活の質を向上させる上で非常に重要です。
特に、立ち座りの動作や日常の介助が必要になった際に、大きな違いが生まれます。 それぞれのメリットについて、さらに詳しく解説しますので参考にしてください。
- メリット1:立ち座りの動作が楽になり、足腰への負担が減る
床から立ち上がる布団の生活に比べ、椅子に座るような姿勢で立ち上がれるベッドは、膝や腰への負担を大幅に軽減します。 - メリット2:布団の上げ下ろしがなくなり、日々の手間が省ける
重い布団を毎日上げ下ろしする作業は、高齢者にとって大きな負担です。ベッドにすれば、その重労働から解放され、時間にゆとりが生まれます。 - メリット3:床のホコリを吸い込みにくく衛生的
床から30cmの高さにはハウスダストなどが舞っていると言われています。床面から高さのあるベッドで眠ることで、アレルギーの原因となるホコリを吸い込むリスクを減らせます。 - メリット4:介護が必要になった際の介助者の負担を軽減する
ベッドの高さを調節できるタイプなら、おむつ交換や着替えなどの介助が必要になった際、介護者が無理のない姿勢で作業でき、腰痛などのリスクを軽減できます。
高齢者がベッドを使う際のデメリットと対策
多くの利点がある一方で、ベッドならではの注意点も存在します。しかし、これらのデメリットは事前に適切な対策を講じることで、ほとんど解消することが可能です。
ここでは、主なデメリットとその具体的な対策方法について詳しくご紹介します。不安を解消し、安心してベッド導入を検討してください。
- デメリット1:設置スペースが必要になる
ベッドは常に一定のスペースを占有します。お部屋が狭い場合は、コンパクトなサイズや折りたたみ式のベッドを選ぶことで対応できます。 - デメリット2:ベッドから転落する不安がある
寝相によってはベッドから落ちてしまう危険性があります。不安な方は、サイドレール(手すり)が付いているタイプや、後付けできるモデルを選ぶと安心です。
【失敗しない】高齢者が使いやすいベッドの選び方5つのポイント
いざベッドを選ぼうと思っても、種類が多すぎて何を基準にすれば良いか迷う方も多いでしょう。ここでは、ご自身の身体の状態や生活環境に合わせて最適な一台を見つけるための、絶対に押さえておきたい5つの選び方のポイントを解説します。
これらのポイントを参考にすることで、失敗のないベッド選びができます。 後悔しないためにも、一つひとつのポイントをしっかり確認していきましょう。
ポイント1:安全な立ち上がりのための「高さ」
ベッド選びで最も重要な要素の一つが「高さ」です。ベッドの高さが適切でないと、立ち上がりが不安定になり、かえって転倒のリスクを高めてしまう可能性があります。
ご自身の身体に合った高さを見つけることが、安全で快適なベッド生活の第一歩です。 具体的な高さの目安と、調節機能の重要性について見ていきましょう。
最適な高さの目安は「膝が90度に曲がる」こと
ベッドの最適な高さは、ベッドの端に深く腰掛け、両足の裏がしっかりと床に着いたときに、膝が90度前後に曲がる高さです。 これより高すぎると足が浮いてしまい、低すぎると立ち上がる際に余計な力が必要になります。
お店で試す際は、普段履いている靴を脱いで確認することが重要です。 この目安を参考に、ご自身の身体にぴったりの高さを見つけてください。
高さが調節できる昇降機能付きベッドも検討しよう
立ち上がる時、車椅子へ移乗する時、介助を受ける時など、場面によって最適な高さは異なります。電動でベッドの高さを変えられる「昇降機能」付きのベッドなら、リモコン一つでいつでも最適な高さに調節可能です。
これにより、日々の動作が格段に安全で楽になります。 電動ベッドの導入を後悔しないためにも、ぜひ高さ調節機能の有無を検討してください。
ポイント2:寝心地と起き上がりやすさを決める「マットレス」
ベッドの寝心地を大きく左右するのがマットレスです。快適な睡眠の質だけでなく、起き上がりのしやすさにも大きく影響します。
ご自身の身体に合ったマットレスを選ぶことは、日々の快適性だけでなく、身体への負担軽減にもつながります。 どのようなマットレスが最適なのか、具体的なポイントを見ていきましょう。
適度な硬さで寝返りが打ちやすいか
柔らかすぎるマットレスは、身体が深く沈み込みすぎて寝返りが打ちにくく、起き上がる際にも余計な力が必要です。逆に硬すぎると、身体の特定の部分に圧力がかかり、痛みの原因になることもあります。
手で押してみて、適度な反発力がある硬さのマットレスを選ぶことが重要です。 これにより、快適な寝心地とスムーズな起き上がりを両立できます。
体圧分散性に優れているか
良いマットレスは、寝たときに身体にかかる圧力(体圧)をバランス良く分散させてくれます。体圧分散性に優れたマットレスは、血行を妨げにくく、床ずれ(褥瘡)の予防にもつながります。
そのため、寝ている時間が長い方には特に重要なポイントです。 身体の負担を軽減し、質の高い睡眠をサポートするマットレスを選びましょう。
ポイント3:身体の状態に合わせた「機能(モーター数)」
電動リクライニングベッドは、搭載されているモーターの数によって利用できる機能が異なります。ご自身の身体の状態や必要なサポートレベルに合わせて、最適なモーター数を選ぶことが重要です。
モーターの数が増えるほど機能も豊富になりますが、その分価格も高くなります。 どのような機能が必要かを具体的に把握し、適切なベッドを選びましょう。
- 1モーター:背上げ機能で読書や食事が楽に
「背上げ(リクライニング)」機能が使えます。自力で起き上がることはできるものの、ベッドの上で上半身を起こしてテレビを見たり、読書をしたりする時間を楽にしたい方におすすめです。 - 2モーター:背上げ+高さ調節で立ち上がりをサポート
「背上げ」と「高さの昇降」機能が使えます。背中を少し起こし、さらにベッドを高くすることで、よりスムーズな立ち上がりを補助します。 立ち上がりに少し不安を感じる方に最適です。 - 3モーター:背上げ+高さ調節+膝上げで最適な姿勢を保つ
「背上げ」「高さの昇降」に加えて「膝上げ」機能が使えます。膝の角度を上げることで、身体が足元にずり落ちるのを防ぎ、より安定した楽な姿勢を保てます。 寝ている時間が長い方や、介護が必要な方におすすめの本格的なタイプです。
ポイント4:転倒・転落を防ぐ「安全性」
高齢になると、わずかな転倒でも大きな怪我につながるリスクが高まります。 そのため、ベッド周りの安全性を高める工夫は、ベッドを選ぶ上で非常に大切なチェック項目です。
ここでは、転倒や転落を防ぐための具体的な安全対策についてご紹介します。安心してベッドをご利用いただくために、ぜひ確認しておきましょう。
サイドレール(手すり)は必要か
サイドレールは、就寝中の転落を防ぐ柵としての役割だけでなく、起き上がりや寝返りの際に身体を支える手すりとしても役立ちます。
必要に応じて後から取り付けられるモデルも多いので、将来的な身体の変化も考慮して検討することをおすすめします。
キャスターにストッパーは付いているか
移動に便利なキャスター付きのベッドを選ぶ場合は、必ず四輪すべてにストッパーが付いているかを確認してください。
立ち上がる際にベッドが動いてしまうと非常に危険ですので、使用時は必ずロックするようにしましょう。
ポイント5:部屋の広さや身長に合った「サイズ」
ベッドを置く部屋の広さや、使う方の体格に合ったサイズを選ぶことも忘れてはいけません。適切なサイズ選びは、快適な療養環境と安全な動線の確保につながります。
ここでは、介助スペースの確保や身長に合わせた選び方のポイントを解説します。設置する場所と使用される方の身体を考慮して最適なサイズを選びましょう。
介助スペースも考慮した幅選び
ベッドのサイズは、寝るスペースだけでなく、介助が必要になった場合のスペースも考慮して選びましょう。ベッドの片側だけでなく、両側から介助ができるように、壁から50cm程度離して設置できる余裕があると理想的です。
一般的なシングルサイズ(幅約100cm)が基本ですが、よりゆったりしたセミダブル(幅約120cm)もあります。 お部屋の広さと介助の必要性を考慮して検討してください。
身長に合わせた長さ選び
多くのベッドの長さは195cm前後が標準ですが、小柄な方向けに長さ180cm程度のショートサイズもあります。
お部屋を少しでも広く使いたい場合や、身長に合うか心配な方は、ショートサイズのベッドも検討してみましょう。
購入?レンタル?介護保険や補助金を活用して賢く導入
高機能な介護ベッドは価格が高額になりがちで、購入をためらう方も多いでしょう。しかし、介護保険のレンタル制度などを活用すれば、費用負担を抑えて導入することが可能です。
購入とレンタルの違いを理解し、ご自身に合った賢い導入方法を選びましょう。 多くの介護用品の購入やレンタルには様々な制度が活用できます。
購入とレンタルのメリット・デメリットを比較
ベッドの導入方法には、購入とレンタルの二つの選択肢があり、それぞれに良い点と注意点が存在します。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶためにも、それぞれの特徴を理解することが重要です。
以下の表で、購入とレンタルのメリット・デメリットを分かりやすく比較しています。 ぜひ参考にして、賢い選択をしてください。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 購入 | ・新品を使える ・自分の所有物になる ・非課税の介護ベッドを選べる | ・初期費用が高額 ・身体状況の変化に対応しにくい ・不要になった際の処分が大変 |
| レンタル | ・初期費用を抑えられる ・身体状況の変化に合わせて機種交換が可能 ・メンテナンスや修理もお任せできる | ・基本的に中古品 ・自分の所有物にはならない ・介護保険の対象外だと割高になる |
身体状況が変わりやすい高齢期には、初期負担が少なく始められ、いつでも機種交換や返却が可能なレンタルがおすすめされることが多いです。
介護保険が使えるのは「レンタル」。対象者と料金の目安
介護保険サービスを利用してベッドを借りる場合、対象者は原則として「要介護2」以上の方と定められています。 この条件に当てはまる場合、所得に応じてレンタル料金の自己負担額が1割〜3割に軽減される仕組みです。
例えば、月額レンタル料が10,000円のベッドの場合、自己負担1割の方なら月々1,000円で利用できます。 ケアプランの作成が必要ですので、まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。
要支援1・2でもレンタルできる?自治体の制度を確認しよう
原則として介護保険によるベッドのレンタルは要介護2以上が対象ですが、例外的なケースも存在します。要支援1・2や要介護1の方でも、医師の意見書などにより必要性が認められれば、レンタル対象となる場合があります。
また、各自治体が独自に実施しているサービスでレンタルできる可能性もあります。 諦めずに、まずはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに問い合わせてみることが大切です。
介護ベッドの購入で補助金は使える?
残念ながら、現在の介護保険制度では、ベッド本体の購入に対して補助金(特定福祉用具購入費)を利用することはできません。 補助金の対象となるのは、腰掛便座や入浴補助用具など、レンタルに馴染まないものが中心です。
ただし、身体障害者手帳をお持ちの場合は「日常生活用具給付等事業」の対象としてベッドの給付を受けられる可能性があります。 こちらも自治体によって基準が異なるため、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。
【目的別】高齢者におすすめの使いやすいベッドをご紹介
これまでの選び方のポイントを踏まえ、どのような方にどのタイプのベッドがおすすめなのか、目的別に具体的なモデルをご紹介します。
ご自身の身体状況やライフスタイルと照らし合わせて、最適なベッド選びの参考にしてください。
シンプルで使いやすい!初めてのベッドにおすすめのモデル
「まだ本格的な介護は必要ないけれど、布団からの起き上がりが辛くなってきた」という方には、インテリアにも馴染むシンプルな電動リクライニングベッドがおすすめです。
背上げ機能(1モーター)だけでも、ベッドの上で読書をしたり、楽な姿勢でテレビを見たりと、日々の暮らしが格段に快適になります。 木製フレームなど、温かみのあるデザインのものも人気です。
狭い部屋や和室(畳)でも置ける!コンパクト・畳ベッドのおすすめ
「ベッドを置きたいけれど、部屋が狭い」というお悩みには、長さが短いショート丈や、幅がスリムなセミシングルサイズのベッドが最適です。 これにより、限られたスペースでも快適な寝室を実現できます。
また、和室の雰囲気を活かしたい方には「畳ベッド」も良い選択肢です。 ただし、畳ベッドは湿気がこもりやすいため、通気性の良いすのこ仕様のものを選ぶのがポイントです。
機能性で選ぶ!人気メーカー(ニトリ・フランスベッド等)のおすすめ電動ベッド
より高い機能性や安心感を求めるなら、信頼できる実績あるメーカーから選ぶのが一番です。 各メーカーが提供する電動ベッドは、それぞれ特徴や強みが異なります。
例えば、「ニトリ」はお手頃な価格帯でデザイン性の高い電動ベッドが揃っています。 また、医療・介護分野で実績のある「フランスベッド」や「パラマウントベッド」は、寝心地の良さや介護のしやすさを追求した高機能な3モーターベッドなど、プロ仕様のモデルが豊富です。各社のウェブサイトやカタログで仕様を比較検討してみましょう。
ベッド周りの環境を整える!あると便利なアイテム
ベッド本体だけでなく、周辺のアイテムを適切に揃えることで、さらに快適で安全なベッド周りの環境を整えることができます。
ここでは、あると便利なアイテムをいくつかご紹介しますので、必要に応じて導入を検討してみてください。
- ベッドサイドテーブル
メガネや薬、水差し、テレビのリモコンなどを手の届く範囲に置けて非常に便利です。 - 見守りセンサー・離床センサー
ベッドからの起き上がりや離床を、離れた場所にいる家族に知らせてくれる機器です。 夜間の転倒リスクなどに備えることができます。 - 防水シーツ
万が一の失禁などに備え、マットレスの上に敷いておくシーツです。 マットレス本体を汚れから守り、衛生的に保てます。
まとめ:最適なベッド選びで、安全で快適な毎日を
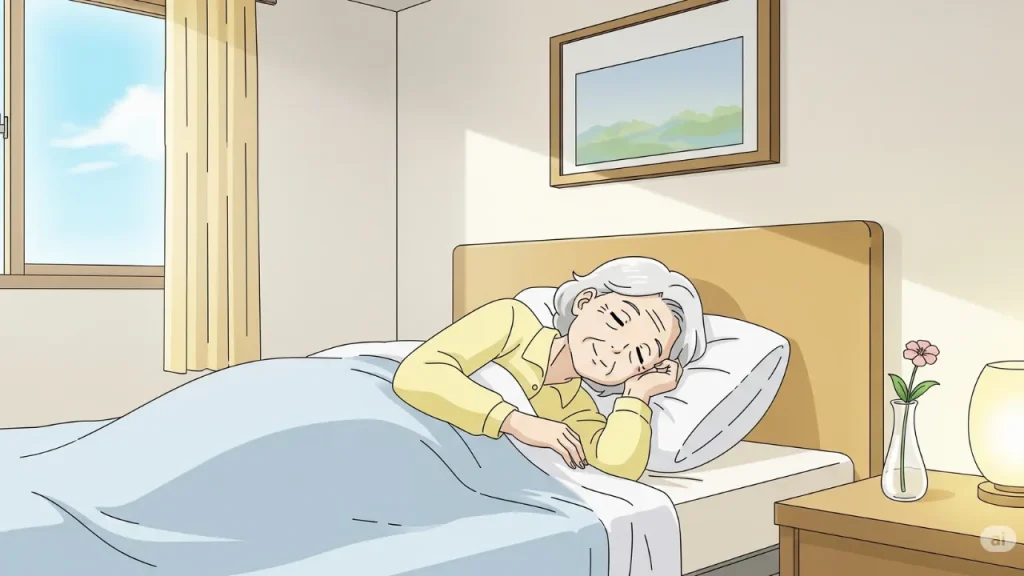
高齢者が使いやすいベッドを選ぶことは、単に寝具を変えるということ以上の大きな意味を持ちます。日々の動作の負担を減らし、転倒などのリスクから身を守り、ひいては自立した生活を長く続けるための大切な投資です。
この記事でご紹介した「高さ」「マットレス」「機能」「安全性」「サイズ」という5つのポイントを参考に、ご自身の身体の状態や生活環境に本当に合った一台を見つけてください。
購入かレンタルか、介護保険は使えるのかといった制度面で迷ったら、一人で悩まずにケアマネジャーや地域包括支援センターの専門家に相談しましょう。 あなたにとって最適なベッドが、これからの毎日をより安全で快適なものにしてくれるはずです。
高齢者のベッドに関するよくある質問
電動ベッドと介護ベッドは何が違うのですか?
明確な定義はありませんが、一般的に「電動ベッド」はリクライニング機能などでリラックスすることを主目的としたものを指すことが多いです。一方、「介護ベッド」は、JIS規格に準拠するなど、介護のしやすさや使用者の安全性がより高度に考慮されています。
高さの昇降範囲が広い、サイドレールが取り付けやすいなどの特徴があります。 ご自身の用途に合わせて適切なタイプを選ぶことが大切です。
高齢者のベッドに最適な高さの目安はありますか?
はい、ございます。ベッドの端に腰掛け、足の裏全体がしっかりと床に着く状態で、膝の角度が90度前後になるのが最適な高さの目安です。
これによって、立ち上がりの際に足に力が入りやすく、安全な動作につながります。
介護保険でベッドをレンタルできる条件と料金を教えてください
介護保険を使ってベッド(特殊寝台)をレンタルできるのは、原則として要介護2以上の方です。 料金は、レンタルするベッドの機種によって異なりますが、その費用の1割(所得に応じて2割または3割)が自己負担となります。
例えば、月額10,000円のベッドなら、自己負担は月々1,000円〜3,000円です。 詳細はケアマネジャーにご相談ください。
要支援1でも介護ベッドのレンタルは可能ですか?
原則として、要支援1・2の方は介護保険でのベッドレンタル対象外です。 ただし、特定の疾病がある場合や、医師の意見書などによって必要性が認められた場合は、例外的にレンタルできることがあります。
また、市区町村が独自に行うサービスで利用できる場合もあるため、地域包括支援センターなどにご相談ください。
介護ベッドの購入に補助金は利用できますか?
介護保険の制度を使ってベッド本体を購入するための補助金はありません。 介護保険の購入費補助の対象は、ポータブルトイレや入浴用品など、レンタルに馴染まない福祉用具に限られます。
ただし、身体障害者手帳をお持ちの方は、別の制度で購入費用の助成を受けられる場合があります。 詳細はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。
ベッドのマットレスの交換時期はいつですか?
マットレスの寿命は素材や品質、使い方によって異なりますが、一般的に5年~10年が目安と言われています。 「真ん中がへこんできた」「寝心地が悪くなった」「スプリングがきしむ」などを感じたら、交換のサインです。
快適な睡眠と身体の健康のために、定期的な見直しをおすすめします。
畳の部屋にベッドを置いても大丈夫ですか?注意点はありますか?
はい、畳の部屋にベッドを置くことは可能です。ただし、いくつかの注意点がございます。ベッドの脚で畳がへこんだり傷ついたりするのを防ぐため、敷板や保護マットを敷くと良いでしょう。
また、畳の部屋は湿気がこもりやすいため、ベッドフレームは通気性の良い「すのこタイプ」を選ぶのがおすすめです。
ニトリで古いベッドの回収はしてもらえますか?
はい、ニトリでは新しいベッドの配送時に、有料で今お使いのベッドを引き取るサービスを行っています。 ただし、購入した商品と「同数量」または「同容量」であることが条件の場合が多いです。
詳しい条件や料金については、ご注文時にニトリの公式サイトや店舗で最新の情報をご確認ください。